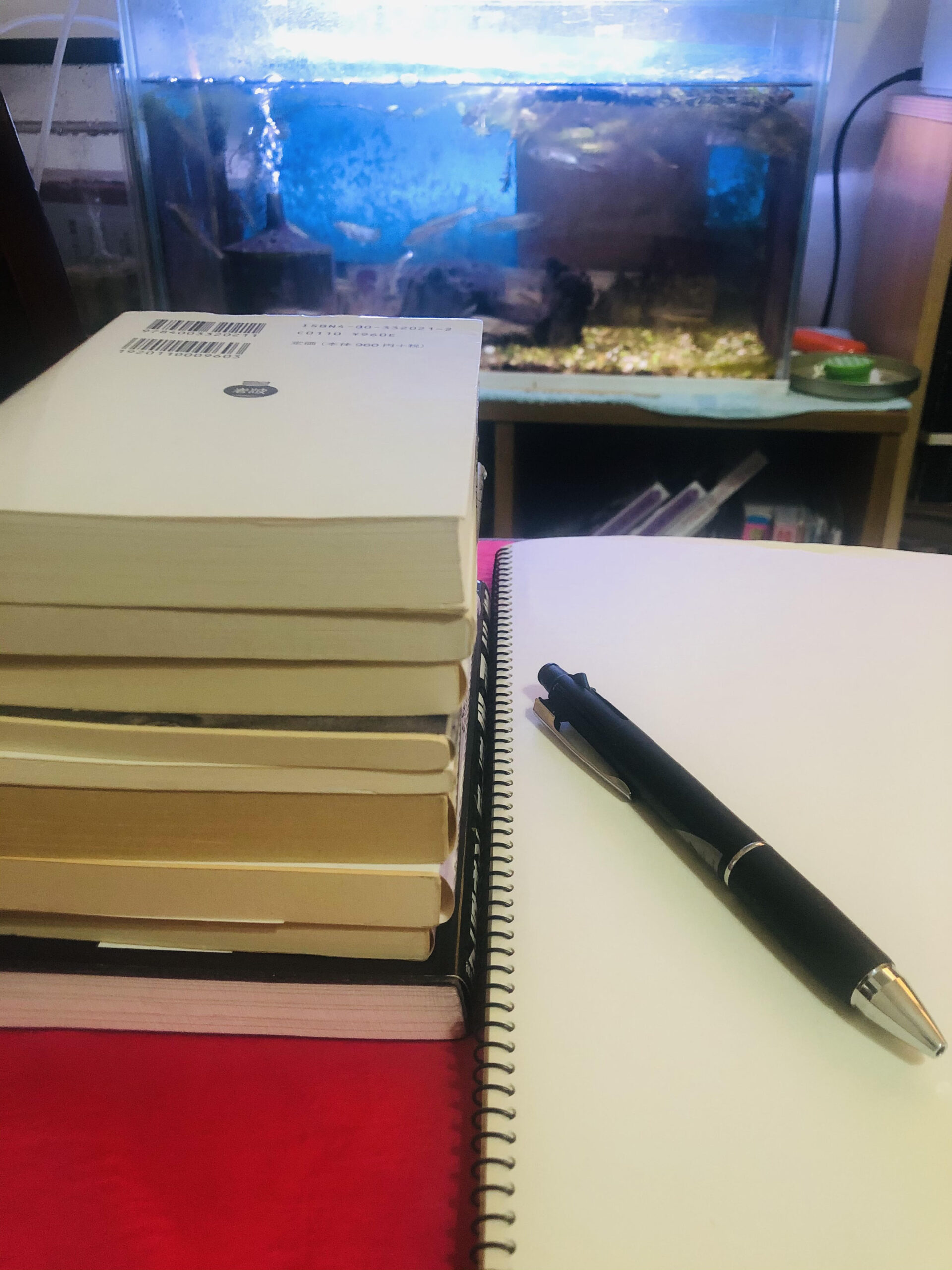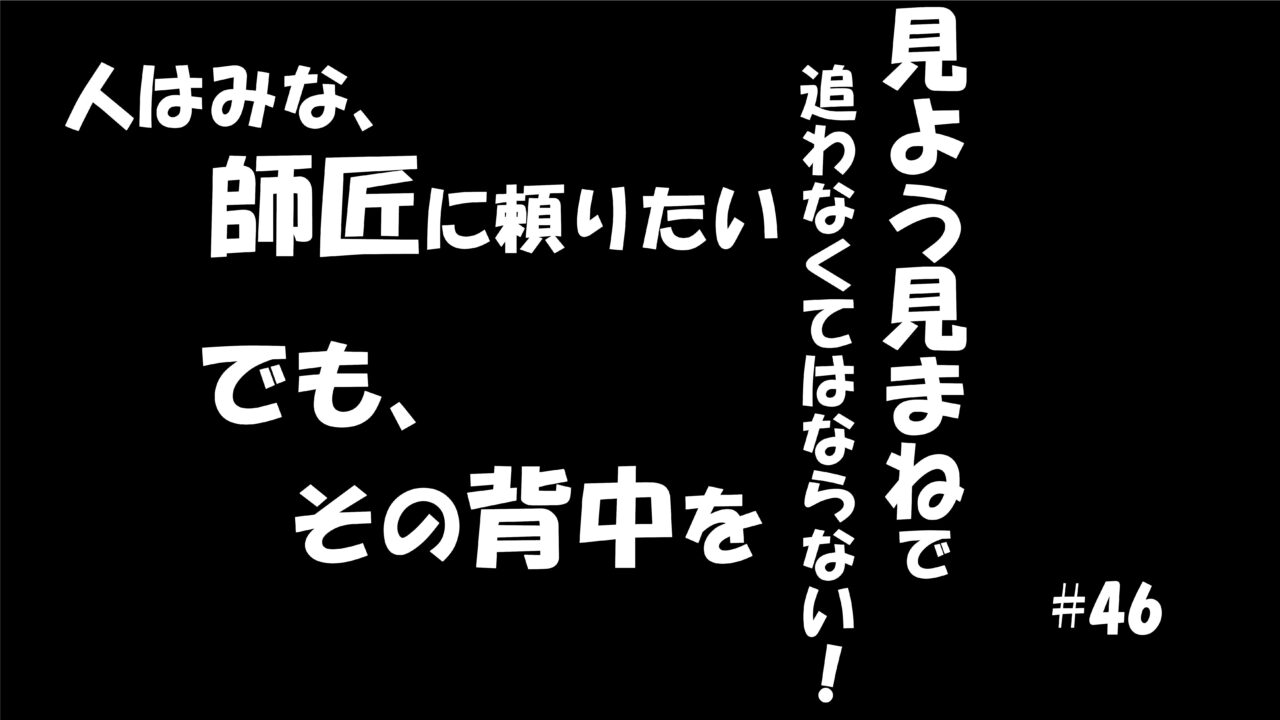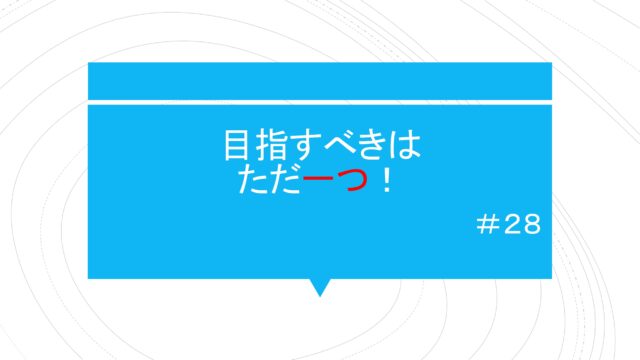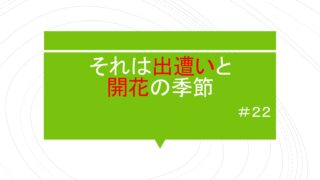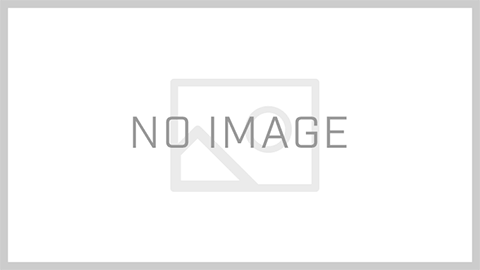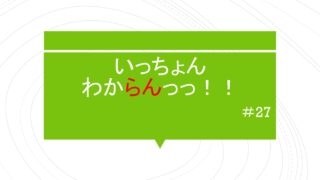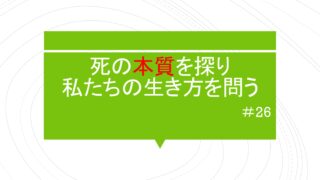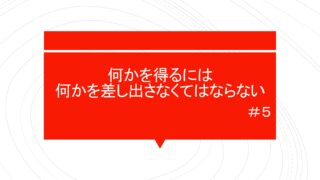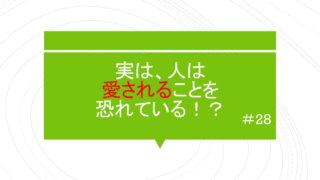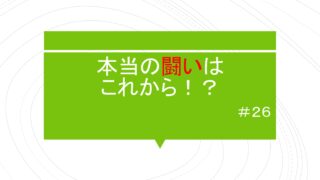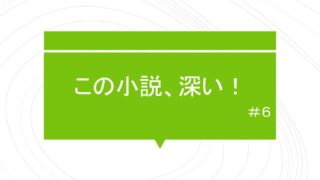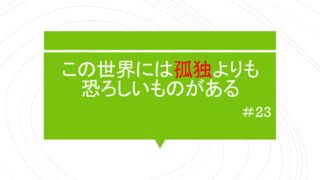うらみわびの【きょう考えたこと】第46回
今日の1冊

指導者の悩み
本質を見失ってしまう
人間は関りのなかで生きている。時には人の下に立ち、時には人の上に立つ。複雑に入り組んだ人間社会においては学習者とも指導者とも成り得る。
ところで、人間を教え導く存在となったとき、私たちは悩むことがある。「私が教えることができるのだろうか」と。
このように考えてしまう原因のひとつとして、自らの経験に即した考え方がある。
職場のことを考えてみる。自分はある程度の期間、その職場に働いている。そして、これから新人の教育係として指導に当たる。自分にはうまく教えられる自信がない。それはなぜか。自らがこれまで経験してきたことが、教育者として足り得るレベルに達していない、と考えてしまうからである。
そういったとき、私たちは教育者をあまりにも神格化しすぎてしまっているのではないだろうか。
教育者は何でも知っている。聞けばなんでも教えてくれる。
もちろん、あらゆるニーズに応える引き出しがあるのは魅力的だし、教育者はそれを目指すべきである。しかしながら、全知全能などということはあり得ないのである。
そして、そのような存在に無理になろうとしてはいけない。「教える」ということの本質を見失ってしまうからである。
このようなケースも考えられる。会社のある部署で十数年の経験を積んだベテラン社員が、その経験を買われてか、いきなり専門外の部署の上役になるケース。
本人はこの人事にとまどうかもしれない。「なぜ、自分がこの部署の上役に?」と。このような心配も、これまでの自分の経験が通用しない、という想いのもとでの心配であろう。
経験とマネジメント
私はこれらの心配はよく分かる。教育において経験こそが財産であるからだ。しかし、経験だけが教育の本質ではない。もう一つの要素、マネジメントという要素も考慮に入れなければならない。
人間は様々な組織に属して活動を行っている。組織があるから上司と部下が存在する。上司と部下が存在するから教育が生まれる。
ここでの教育は単に仕事のノウハウを教えることにとどまらない。上司は部下を導く存在である。
つまり、自らの組織が一つの生命体として活き活きと活動するために組織の構成員のモチベーションを良好にしていくことも上司の重要な役割である。これこそが組織のマネジメントである。
組織のマネジメントは一朝一夕に培われるものではない。組織を導く力、これも立派な才能であり、能力である。『論語』では孔子が以下のように言っている。
上礼を好めば、即ち民は敢えて敬せざること莫し。
上義を好めば、即ち民は敢えて服せざること莫し。
上心を好めば、即ち民は敢えて情を用いざること莫し。
夫れ是くの如くんば、即ち四方の民は其の子をきょう負して至らん。
いずくんぞ稼を用いん。
孔子 『論語』 巻第七 子路第十三の四
(上の者が礼を好めば人民はみな尊敬するし、
上の者が正義を好めば人民はみな服従するし、
上の者が誠実を好めばみなまごころを働かせる。
まあそのようであれば、四方の人民たちもその子供を背負ってやってくる。
どうして穀物づくり(を習うこと)などいるものか。
※訳は金谷治 訳『論語』 岩波書店(1999)による。
これは、樊遅(はんち)という人物が穀物づくりを教えて欲しい、と言ったときの孔子の返答である。
樊遅の頭の中には、農民の悩みは自身が農業を経験しな変えれば分からない、という考えがあったのでしょう。この時点で樊遅も素晴らしい考えの持ち主である、と私は思います。
しかし、人間には得意なこと、苦手なことがあり、やるべきこと、他の人に任せるべきこと、あります。まじめな人ほどこれらを、「やりたいこと」、「やりたくないこと」という二項におとしこんでしまう。それではもったいない。
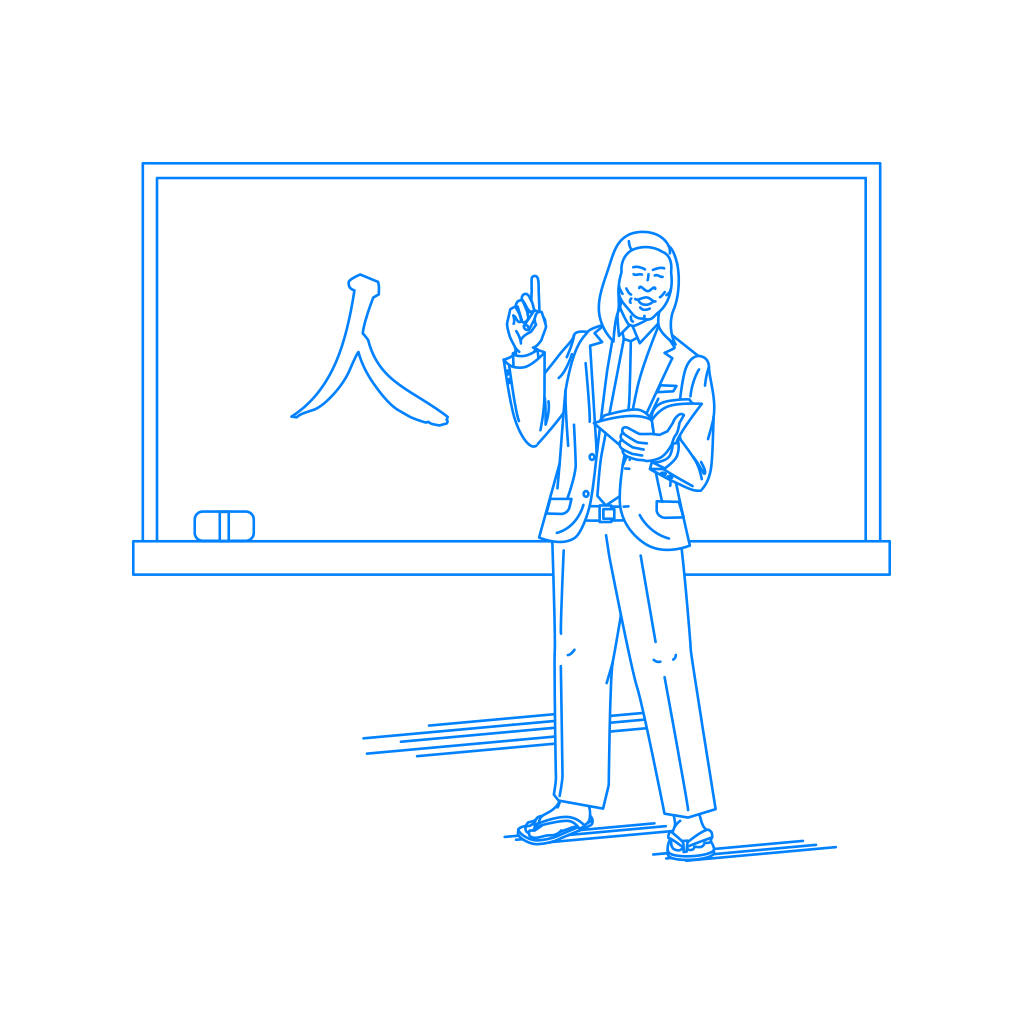
製造業の会社を見れば分かりやすいかもしれない。製造業の事業のメインは製品をつくり、販売すること。突き詰めれば、製品をつくる、ことである。
どれが欠けてもいけない
製品をつくるのは職人である。一方で、職人をまとめ上げる人、人的ネットワークを駆使して製品を売り込む人、会社を経営する人もいる。そして、後者の人たちこそ、会社にとっては人をまとめ上げ導く存在である。
他方、そのような指揮官たちが現場の製造に精通しているか、と聞かれたらそうとは言い切れない。製造に関していえば、現場でモノを造っている人たちの方が経験は圧倒的に多い。会社の構成員にはそれぞれの強みとなすべき使命がある。どれが欠けてもいけない。
そのなかで人をまとめ、導く存在を任される、ということ。それは当人にしかできない素晴らしい仕事なのである。
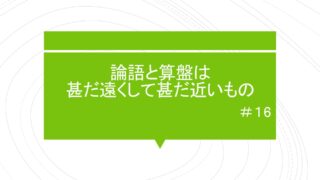
日本の首相が辞意を固め、次の自民党総裁選が近日の政治的話題に上がっている。菅氏が優位に進めているようである。
菅氏はこれまで安倍政権で官房長官を歴任してきた。あらゆる省庁の官僚の人事権を担う職を続けてきた菅氏が次期総理大臣の職に就こうとしていることは、上記の「マネジメント」という観点からみれば興味深い。
「会見をするだけの人」、「外交が苦手」等、様々な不安説もあるが、総理大臣の下に各閣僚、そして官僚たちがいるのが現行の体制である。ここから考えると、菅氏のマネジメント能力の高さ。ここに期待するところは大きいのではないだろうか、と個人的にはみている。
人には個性がある。様々なことに挑戦し、自らの個性を確認する。そして自らの能力を最大限に発揮して羽ばたける、そんなフィールドを模索することが大切である、と思う。
今日も皆さんが幸せでありますように!