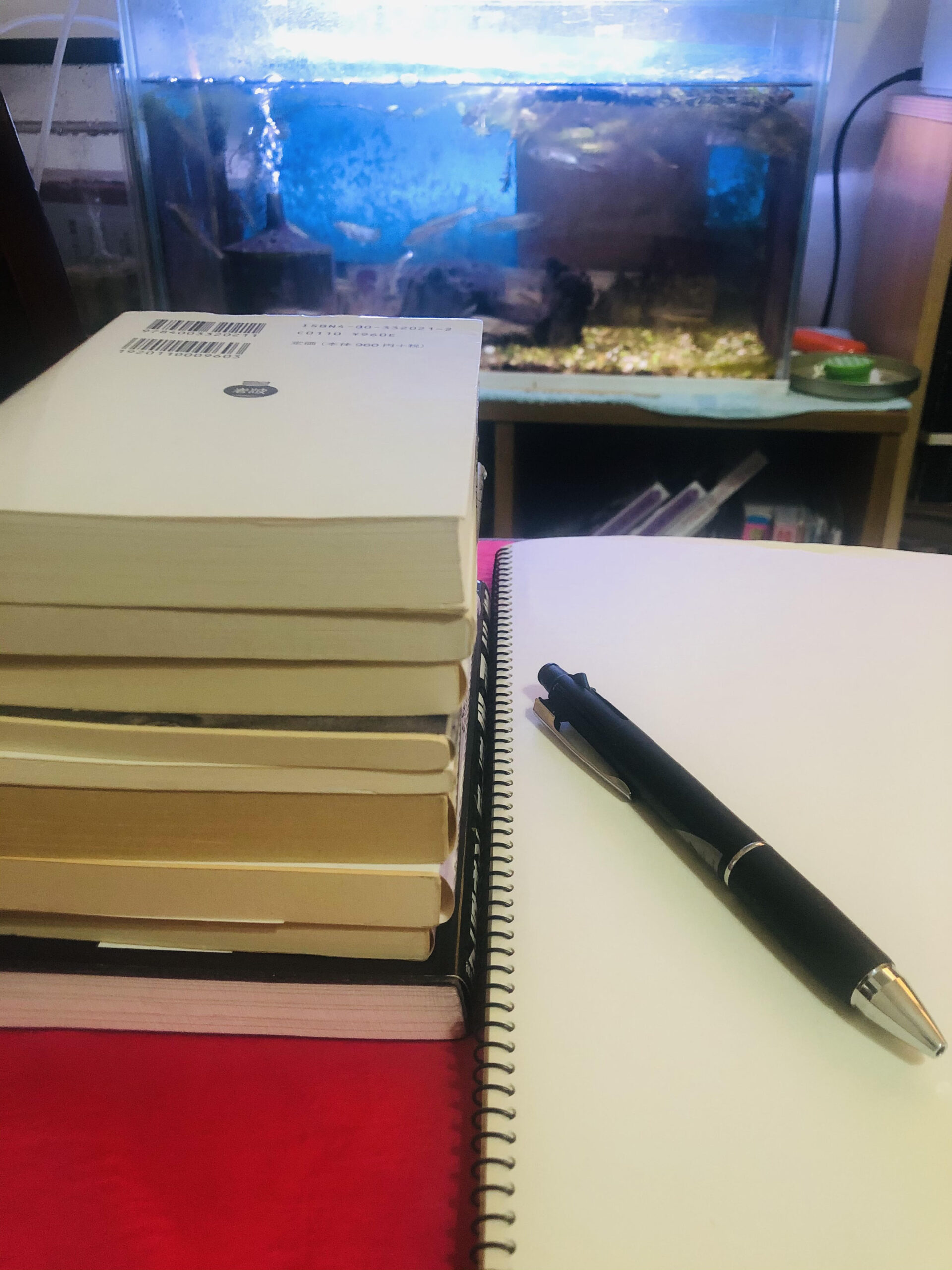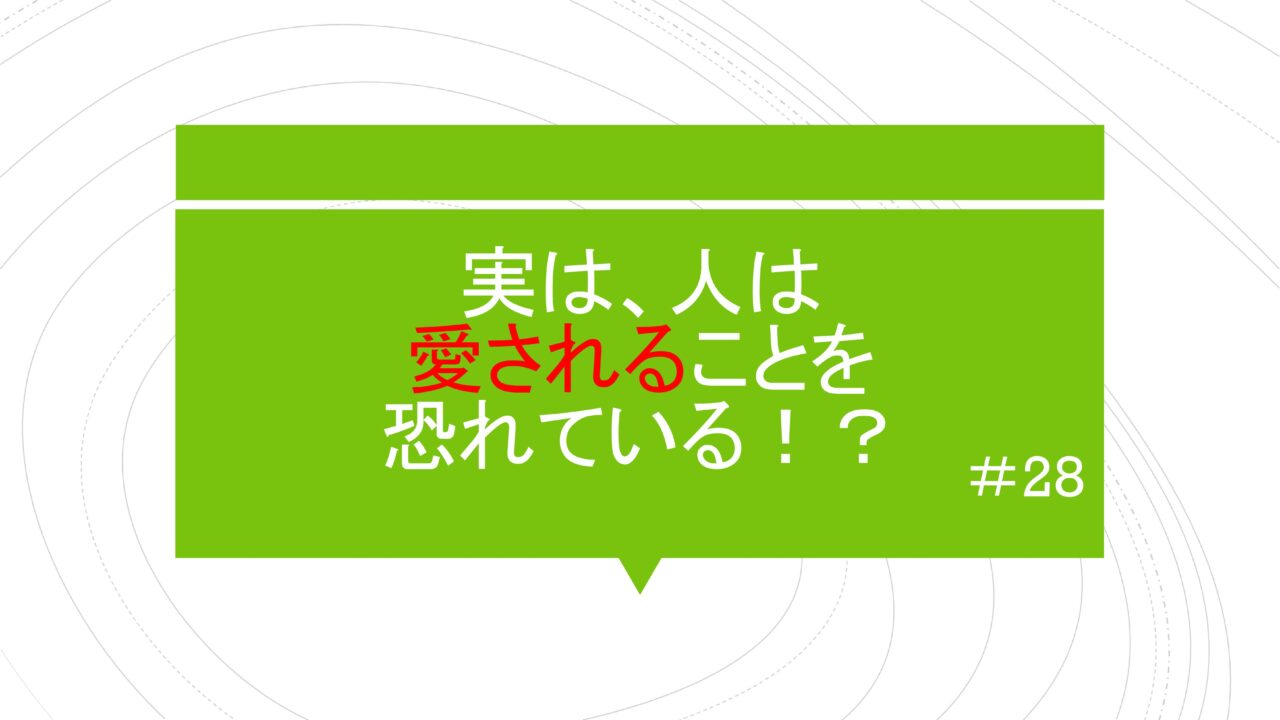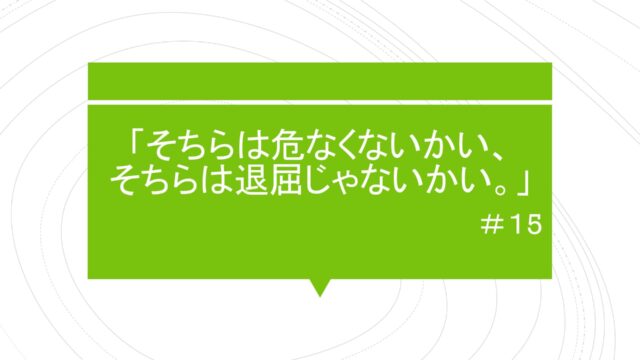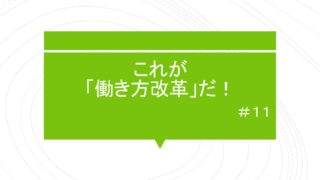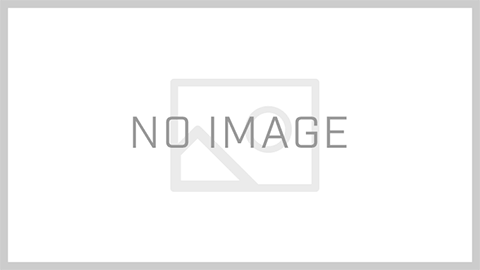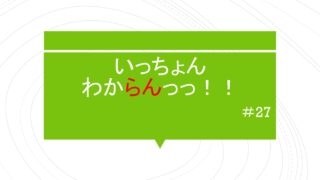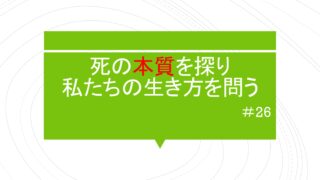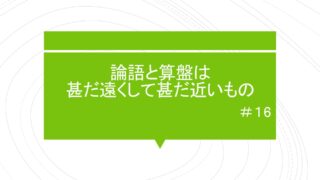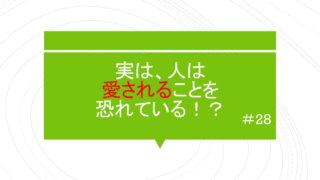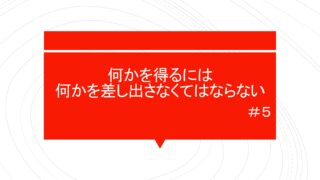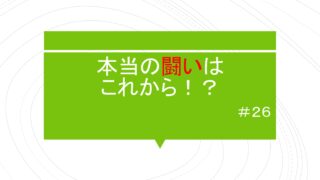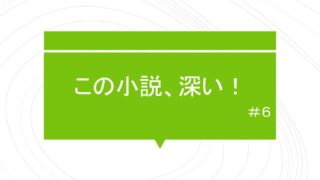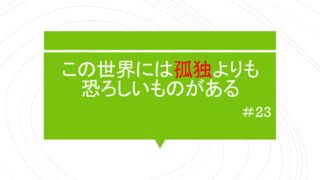久しぶりに食べたチョコボールがおいしい!
今回はタイトルは知ってたけど、よく内容は知らなかった1冊から入ります。
うらみわびの【この本がおもしろい!】第28回
カミュ『異邦人』
我が道を行く
人の数だけ心があり、考えがある。誰一人として同じ人はこの世にいない。みんな違ってみんないい…… そうのように思うことはあっても現実は異なる、という感触もある。私たちが活きるのは「本音と建て前」の世界。パーソナルスペースから一歩踏み出せば、そこに広がるのは「常識」が支配する世界。「わがまま」が通じない世界。出る杭がうたれる世界。そこに生き苦しささえ感じる。
一方で「我が道をゆく」という生き方を貫く人もいる。私はそのような人を尊敬するし憧れもする。しかしながら、そこにも度があるようで……。
今回紹介する1作目の小説、カミュ作『異邦人』の主人公ムルソーはそんな「我が道」を行き過ぎた人だ。彼にとって大切なのは「今、目の前にあるもの」。具体的なものにしか興味を示さない彼にとっては、「今、目の前にあるもの」、それだけが目的であり判断材料である。
しかし、彼のような自由奔放で脈絡がなく、予想がつかない人物の存在を社会は許さない。もちろん、ムルソー自身も過ちを犯す。しかし、その過ちを社会がどう断罪するのか。そこに『異邦人』という小説の神髄がある。
 |
|
価格:605円 |
![]()
| 勝手に評価表 | |
|---|---|
| 内容 | ★★★☆☆ |
| 難しさ | ★★☆☆☆ |
| 価格 | ★☆☆☆☆ |
ところで『異邦人』のムルソーという人物は三浦綾子の小説『残像』の栄介に似ている。
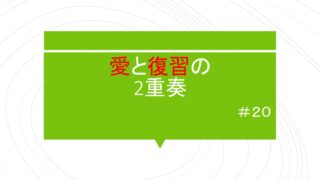
作中で「栄介さんとの子供を身ごもった」という女性が現われるのだが、「そんなの知らん」と突っぱねる。後にその女性は自殺してしまう。なんともクズ野郎な栄介。しかし『残像』の興味深いところは、そんなクズ野郎栄介と教師である彼の父を対比させるところにある。反省の念に駆られる聖職たる教師という善と自分の価値観を貫くブレない悪、はたしてどちらがより清らかな生き方なのだろうか。哲学者であるハンナ・アーレントによれば「善を為すとも悪を為すとも決めることのできない人間が最大の悪を為す」という。つまり優柔不断であり続けること自体が自身にとっても他者にとっても良くないことである、というのである。
座して天命を待つ
物語ではムルソーに死刑判決が下る。それでもなお、ムルソーは自らの信念を曲げずにひたすら死を待つ。ここで想起されるのが『ソクラテスの弁明』だ。古代ギリシアの哲学者ソクラテスは、ひたすら相手に問いを続けることで相手から考えを引きだす、という問答法を考案し、市民に”教養”を広めようとした。しかしながら、一般市民の教養化は一部のエリート市民たちが合議によって政治を行う、という当時の社会になじまなかった。結果としてソクラテスは異端裁判にかけられる。『ソクラテスの弁明』はその裁判でのソクラテスの弁明に始まり、牢獄での弟子プラトンとの会話を記したものである。
 |
|
ソクラテスの弁明・クリトン(プラトン) (岩波文庫 青601-1) [ プラトン ] 価格:572円 |
![]()
| 勝手に評価表 | |
|---|---|
| 内容 | ★★★★☆ |
| 難しさ | ★★★☆☆ |
| 価格 | ★☆☆☆☆ |
本書で驚かされるのは、ソクラテスが裁判では饒舌に自らの無実を訴えたのに対し、死刑判決が下ってからは、座して死を待つ、という姿勢である。プラトンはソクラテスを失うのは社会の損失である、として脱獄、つまり生きることを勧める。しかしそれをソクラテスは拒絶するのだ。
天才はつねに遅咲きである。「音楽の父」とよばれるバッハが名声を集めたのはその死後だそうだ。ここから考えさせられることがある。私たちは誰からか評価されることではなく、自らがしたいこと、正しいと思うことをやればいい、ということである。そこには2つの視点がある。第1に多くの人々に評価されたものがすばらしい、とは限らない。たとえ少数の人間に良し、といわれたものにも、多くの人々に評価されたものと同等の価値があるのではないか。なぜなら、あなたの功績が目の前の一人の人間の心を打ったことはまぎれもない事実なのだから。
第2に他者の評価抜きにして自らがやりたいことをやる、これこそが満足感と幸福感の源泉であると信じているからである。このためには仕事と趣味は切り離して考える必要も出てくるだろう。ぶっちゃけ仕事とはお金稼ぎである。お金は人々の評価の見返りである。良い仕事の定義としてお金が儲かる仕事とする。するとよい仕事とは多くの人から評価される仕事ということになる。(そこに「やりがい」や「誇り」が足されればgood!)
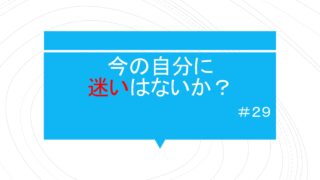
一方で私たちの幸福にとって欠かせないのが「生きがい」である。その源泉が趣味である。運動であり、芸術である。私が思うに人生のウエイトでみると 趣味>仕事 でありたい。単純に一日の中でそれぞれに費やす時間ということで考えるとどうしても仕事に撮られる時間が多くなるのは事実。それでも時間の充実度・重要度においては趣味こそが私たちの人生に必要であると考える。だからこそ「趣味の時間をどう確保するか」、「趣味に使うお金をどう捻出するか」という視点で仕事を考えるようにしている。趣味から人生を見るとまた違った景色が見えてくるのではないだろうか。
さて、ソクラテスの話に戻そう。彼は最後まで自らの姿勢を貫いた。それは「生きる」という観点からすれば死を選ぶことであり合理的ではない。しかし、彼は自ら死を選ぶことでその精神を最後まで生かすことにしたのである。彼は裁判に勝つこと(陪審員の過半数を納得させること)ではなく、自分の意見を最後まで貫き通した。彼は他者から評価されることではなく、自らのスタンスを貫いたのだ。その生き方に感銘を受けた。彼の言説を扱った書は現代でも十分に読まれるに値する。