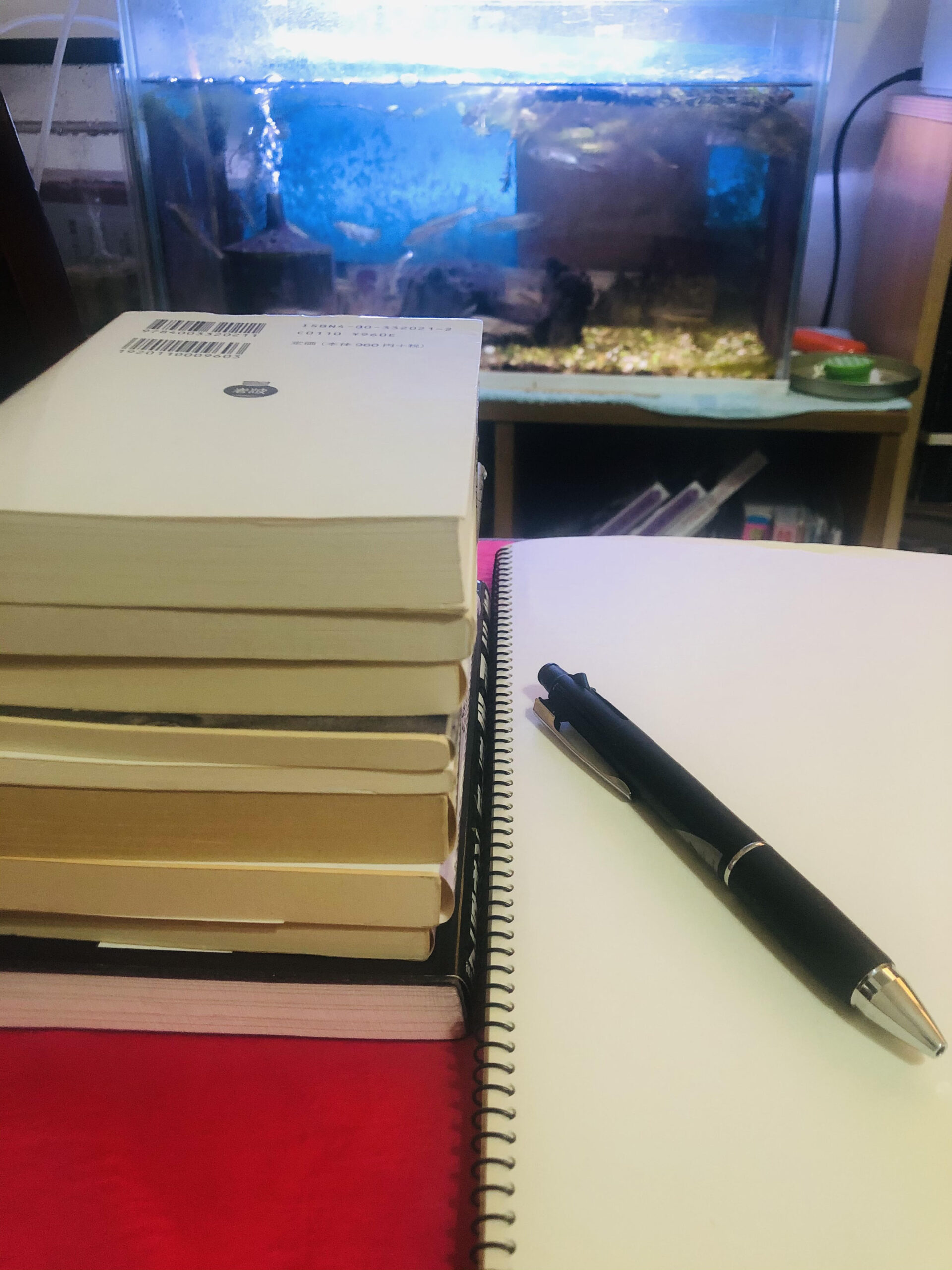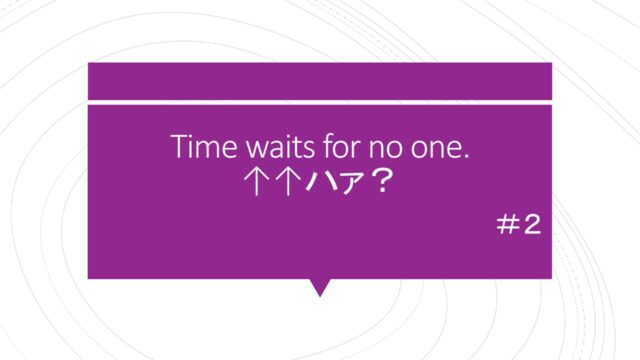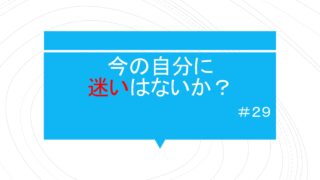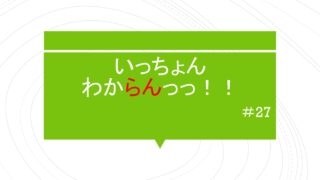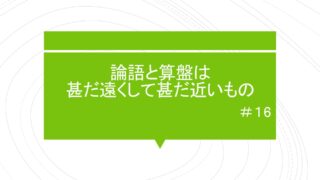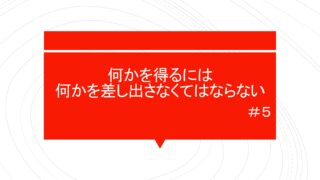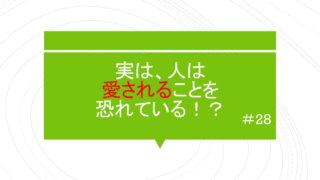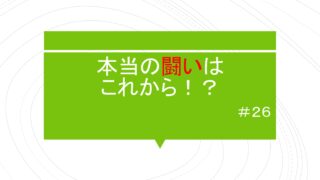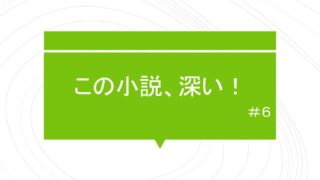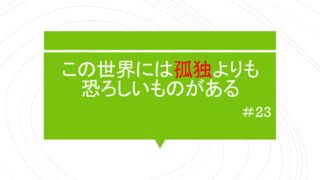幸せな人生
読み切った感想としては「いや~いい話だ」、というのが率直なところです。どこがいいかというと、この話にでてくる登場人物たちがそれぞれ心の底に沈んでいた悩みがパッと和らいでいくというか、絶望の人生に希望の光を見出している、というところに心がじんわり温かくなったんです。
ここに出てくる話のほとんどが登場人物の「死」ということを考えると決してハッピーエンドではないかもしれない。むしろ様々な人の死を見届けてきた犬、「多聞」は死神と捉えることも可能だ。しかし、多聞を含め死んでいった人たちが不幸な死を遂げたようには私は思えない。人生というものは全体をトータルでみる見方もできるが、その節々や「今」という時点における幸、不幸でみることもできる。後者でみるならば、彼らはやはり幸せを感じながら死んでいったのではないだろうか。幸せに生きる道を見出したのだから。
幸せに生きる道。それはなにも天から降ってきたものではない。それはもともと自分の内に眠っていたものなのだ。それを多聞が呼び起こしたに過ぎない。(その多聞もすごいのだが)
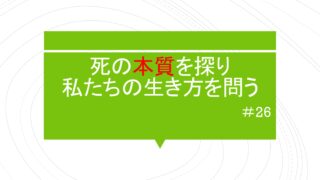
それは、野球で例えると、キャッチャーを変えた瞬間にピッチャーが見違える投球をすることがあるのに似ている。お互いの波長が合っているのだ。
波長。人生における人間関係においてこの存在を考えることもある程度、有意義であろう。人間にはもともと合う、合わない、があるものだ。
ある環境で成果が出ないのは単に自分の能力、努力が不足しているだけではない。その環境そのものが自分に合っていないのかもしれない。それがよくうかがえるのが紗英と大貴の関係だ。お互いの波長が合わないことはお互いに承知している。それでも並行性のまま生きている。生計が立てば相手の存在は関係ないのかもしれない。そんなドライな家庭もある。
しかし、紗英は愛のある家庭を求めている。これが決定的だ。愛のある家庭は幻想なのか。毎日とはいえない、それでも目指していくべきだ。目指していくこと自体が有意義な人生なのかもしれない。
自分の理想と居場所
大きな一つの時間の流れを一匹の犬が貫く本作であるが、この犬は出会う人々によって多様な姿を見せる。ある時は多聞となり、またある時はショウグン、クリント、アルベルト・トンバ、レオ、ノリツネへと変化していく。1つの場所を目指す同じ犬なのであるが、飼い主の目を通すと別の顔に移るのだ。
私たち人間もそうなのではないか。仕事での自分、プライベートでの自分。本名を名乗ることもあればニックネームやペンネームで名乗ることもある。違う役割を果たす自分だけどやっぱり本質的には同じ自分だ。
他者から自分への評価というものは大概、「私」の一側面しか見ていない。思えば、そこに一喜一憂するのも大げさなような気もしてくる。私を一番よく知っているのは私なのに、なぜここまで落ち込むのだろうか。実はそれだけ「理想の自分」を追い求めて、周りからの評価を気にしている証拠である。
理想の自分像はあるのになかなか思うようにはなれない。そもそも理想というものは常に私たちのはるか先にあり、決して到達することのできないものなのかもしれない。それを思えば現在の自分に妥協するのも一つの生き方であるが、一方で社会がそれを許さないことも事実だ。
だからこそ、居場所が必要だと考える。誰からも批判されない自分を肯定できる、もしくは自らの過ちを認めつつ、それを含めて肯定できるグループが必要である。
その基本が家庭である。しかしながら結婚などを通して他者と交わると、家庭内にもなかなか自分の居場所がない、という場合がある。その場合は空間だけでなく、時間で自分の居場所を作る必要がある。毎晩9時以降は「自分の時間」をつくる、といった具合に。

加えて、お互いの良い・悪いを素直に認め合い、そのうえでお互いに助け合うこと、その雰囲気の醸成というのも欠かせない。
夫婦であればお互の不満を否定を前提とせずに吐き出す場もあったほうがいい。自らの欠点を指摘されるのは決して気持ちのいいものではないが、家庭内に秘密はないほうがいい。
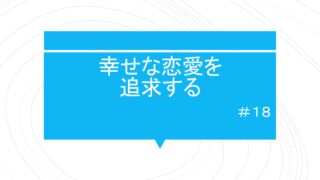
抜け出せない貧しさ
本作には犯罪者も出てくる。犯罪そのものは決して肯定されるものではないが、犯罪者が歩んできた人生は憂うべきものに感じた。「罪を憎んで人を憎まず」だ。
どうしても抗えないものが人生にはある。生まれながらの貧しさがそれだ。資本主義経済では自由競争が根底にある。競争により洗練された価値のあるモノが生み出されるのは確かであるが、一方で競争に負けたものは自業自得である、という自己責任論が見え隠れする。
貧しさは自己責任なのか。そうではない。貧しさは農作物の不作といった抗えない自然によるものや体制の変化といった政治的なものも関わってくる。
近年では国家やイデオロギー間における紛争の被害者が後を絶たない。彼らは自業自得なのだろうか。その被害者たちが自らの力で生きていくことをサポートするのが政治や社会における勝ち組の使命のようにも感じるが、それができていないというのも現状である。
残された弱者は生きていくために手段を選べない状態に陥る。清く正しく生きたくても手段がない。これほど悲しいものはない。
本書には実に多様な人生が描かれており、同時に皆が心になにかしらの闇を抱えて生きている。そしてその闇を癒してくれるのが一匹の犬の存在であった。苦しみの少ない人生にこしたことはないのであるが、現在で捉えたときに幸せな人生、そして大切な存在との出会い。それらを大切にして生きていきたいものである。
今日も皆さんが幸せでありますように!