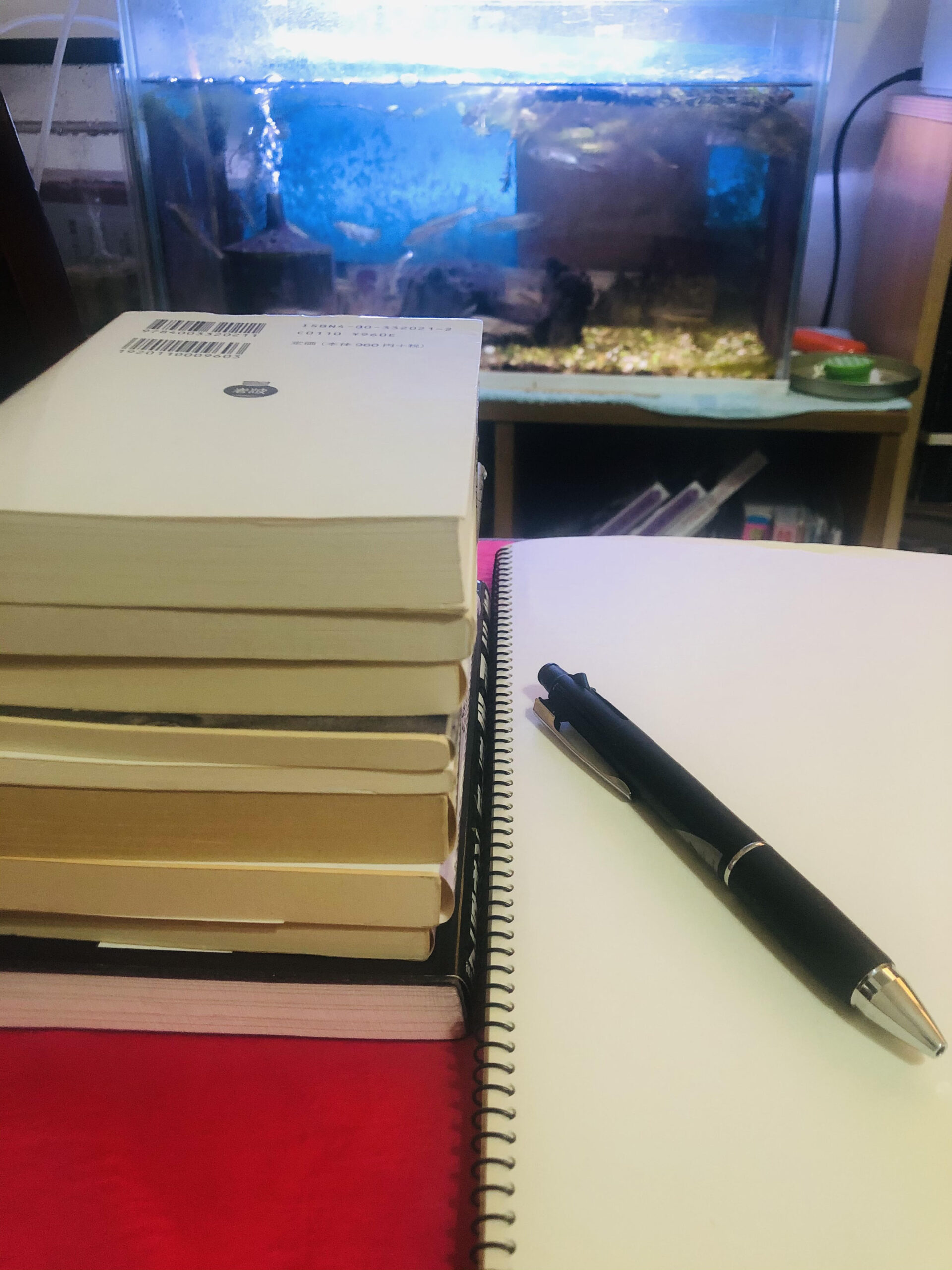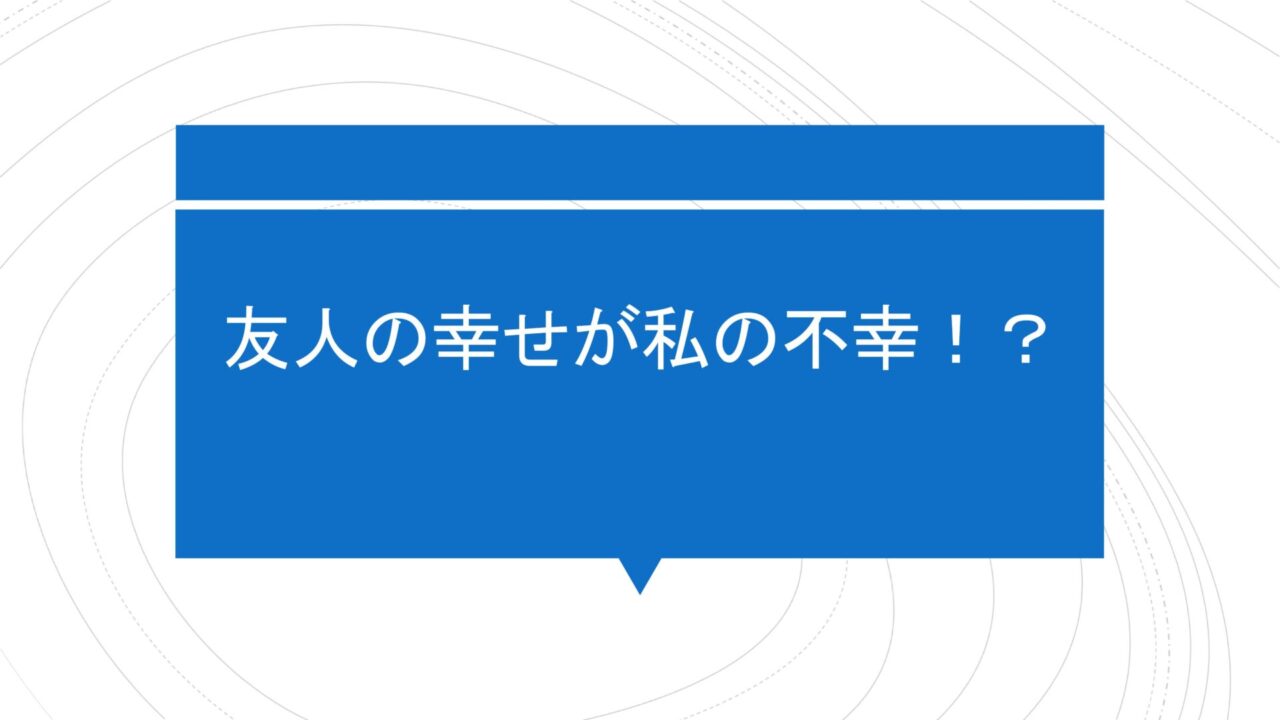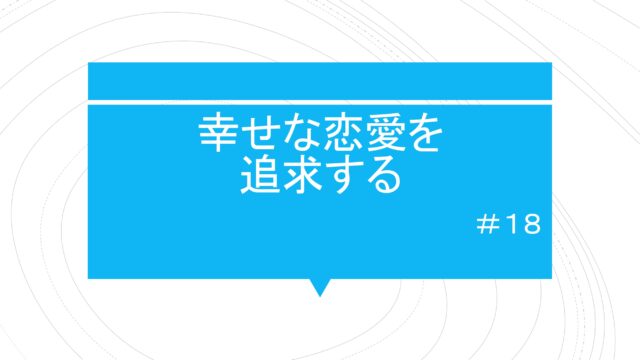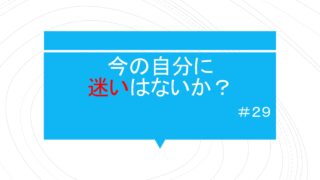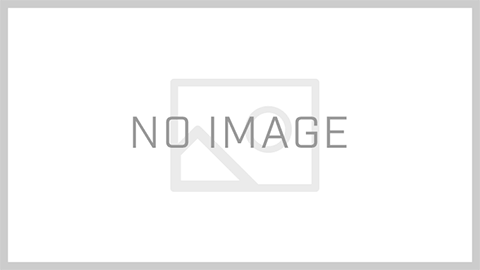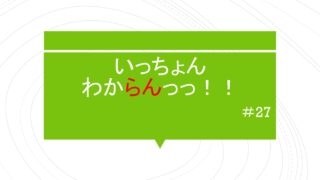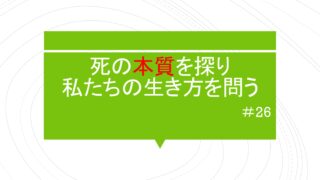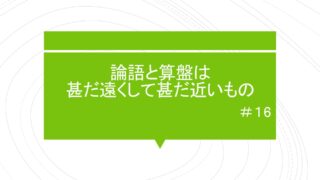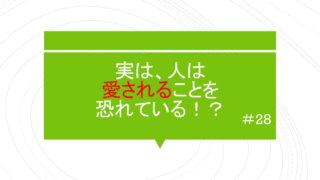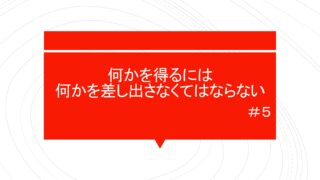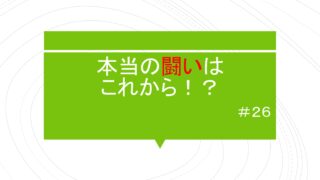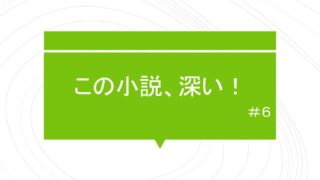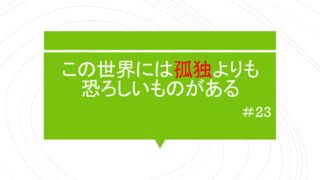不幸によって成り立つ幸せ
「人の不幸は蜜の味」という。
「私は幸せになりたい」と言いながら、仕事で同僚が失敗すると安堵する心がある。
友人の結婚式に出席する私。喜ばしいことのはずなのに自らの心は晴れない。友人の幸せが自らの不幸となっている。
この矛盾をどう説明すればいいだろうか。
結局のところ、私たちの求める”幸せ”とは他者との比較によって成り立つ相対的なものなのだろうか。
もし”幸せ”とは、私たち個人が追い求めるものであり、他者との比較によって成り立つものではないとすれば、私たちは主観的な視点によって”幸せ”、を追求しなければならない。幸せの主語を”他者”から”私”にするのだ。
私たちが他者の不幸を見て安心するのは、”幸せ”とは不幸の度合いによって感知できるものであるからであろう。
つまり、自らが不幸度80%ならば幸せとはいえない。自らが不幸度20%ならばまずまず幸せである、といえる。
私たちの”幸せ”は他者の状況によっても変わることがある。他者の不幸度が80%ならば私の幸福度が上昇する、ということがあるのだ。これは不思議なことである。
以上よりいえることは、私たちは自らの”幸せ”を求めながら、同時に同じ理由から他者の不幸を望んでいる、ということである。意識の程度の差はあれど、他者の失敗をみて、どこか心が落ち着くところがあるのはそのためである。
心と身体の乖離
フランスの哲学者アランは「情念が人を不幸にする」と言った。情念とは私たちの身体の自然な反応に対して心が「こうしたい」、「こうでありたい」と思うことである。
つまりアランが言いたいことは、「こうあるべきだ」、「こうしたい」と自らが考えるが、身体が思うように動かない。こういった体と心の乖離が人生がうまくいかない原因である、というのである。
アランの言う通り「情念が人を不幸にする」ならば、私たちに求められるのは、自らの身体の反応に従う、ということだ。
これを”幸せ”についてあてはめると、他者の失敗をみて安堵する私たちの心こそが自然な反応といえる。この心の反応を否定せずに自然な反応として受け止めてあげる必要がありそうだ。
しかしながら、他者の不幸を自らの幸せの条件とすることには承服しかねる。私たちの”幸せ”はあくまでも”幸せ”と感じる項目の積み重ねによって、”幸せ”は”幸せ”によって計測されなければならない。
集団で考えるならば、他者の成功が自らの成功でもあり、他者の幸福が自らの幸福でもあるのだ。
友人の結婚式で私が不幸を感じるのは、私が自らの”幸福”を第一に考えている裏返しともいえる。それを踏まえて自らを含めた”私たちの幸福”も考えていけたらよい。
これはきれいごとかもしれない。社会は競争で成り立っている。成功者の裏には敗者がいる。
それでも1位とそれ以外にはたしてどれほどの差があるのだろうか。これについては人々によって異なる”幸せ”の定義についても考えていかなくてはならない。
所得が生む幸せ
所得が幸福のバロメーターであるとするならば、二つのことが言える。
1、結果が幸福を産むということ
2、他者からの評価が幸福に結びつくこと。
1については明白である。お金がもらえるのは自らが誰かに何かを提供した見返りである。換言すれば、自らの好意によって誰かが利益を得たときの報酬である。そこには確かな結果が存在する。
人によっては私たちの提供するサービスに満足して、再びサービスを受けに来てくれる顧客もいる。その行動は顧客が私たちのサービスを評価してくれていることを意味する。私たちはこの評価がうれしい。それは私たちの出した結果に対する評価だからである。
お金がない、という状況は不幸を生みやすい。であるならば、私たちは他者から評価される結果を出さなくてはならない。
一方で、親の保護のもとで生活の不安なく過ごした日々。幸福への感受性が高かった日々が遠ざかってしまっていることも合わせて想起したい。大人になることで私たちは幸福の大切なパーツを失ってしまったのではないか。
大人になることで親の保護は受けられない。しかしながら、最低限の安定した生活のなかにも確かな幸せがあるような気がしてならないのである。