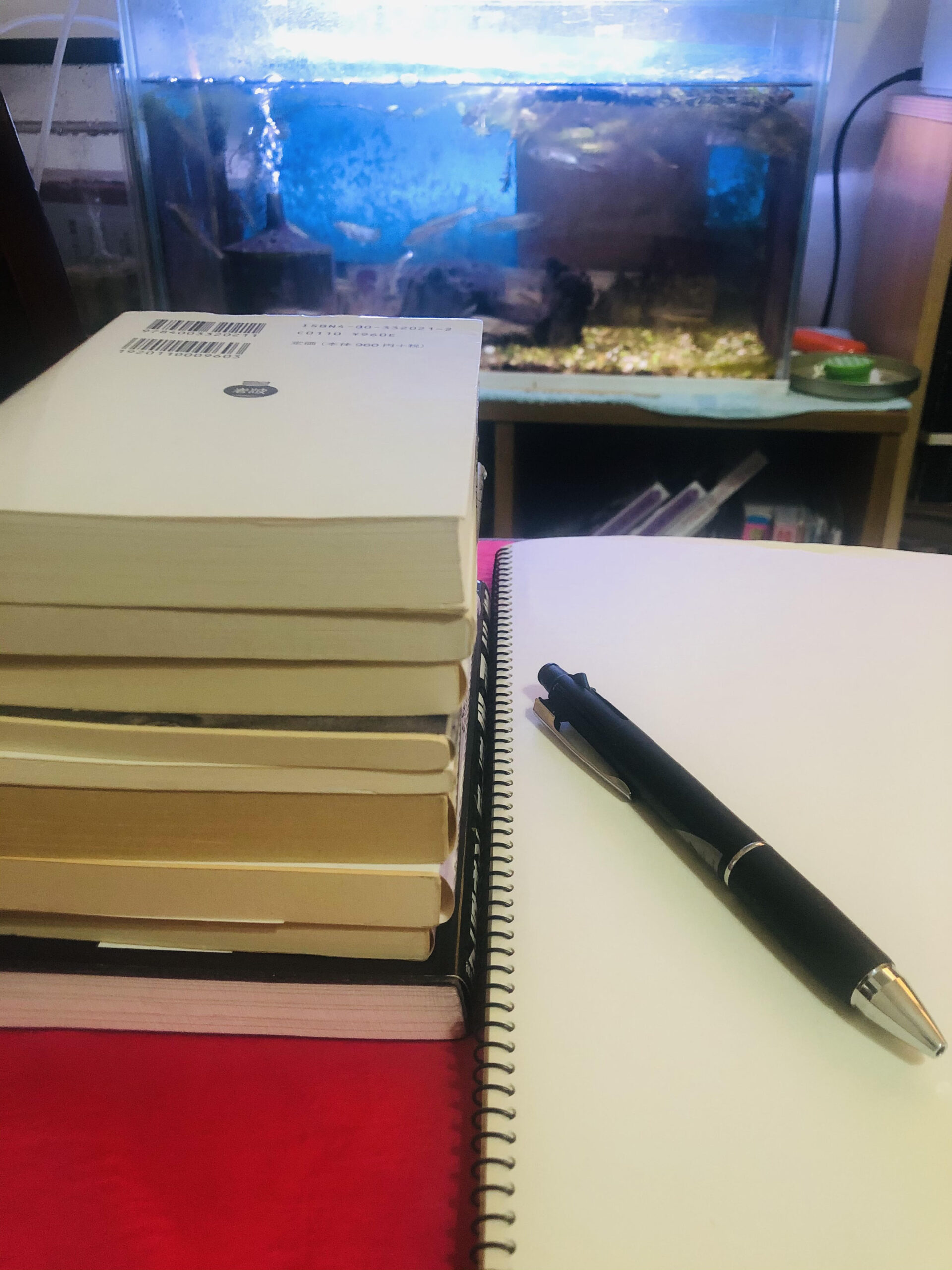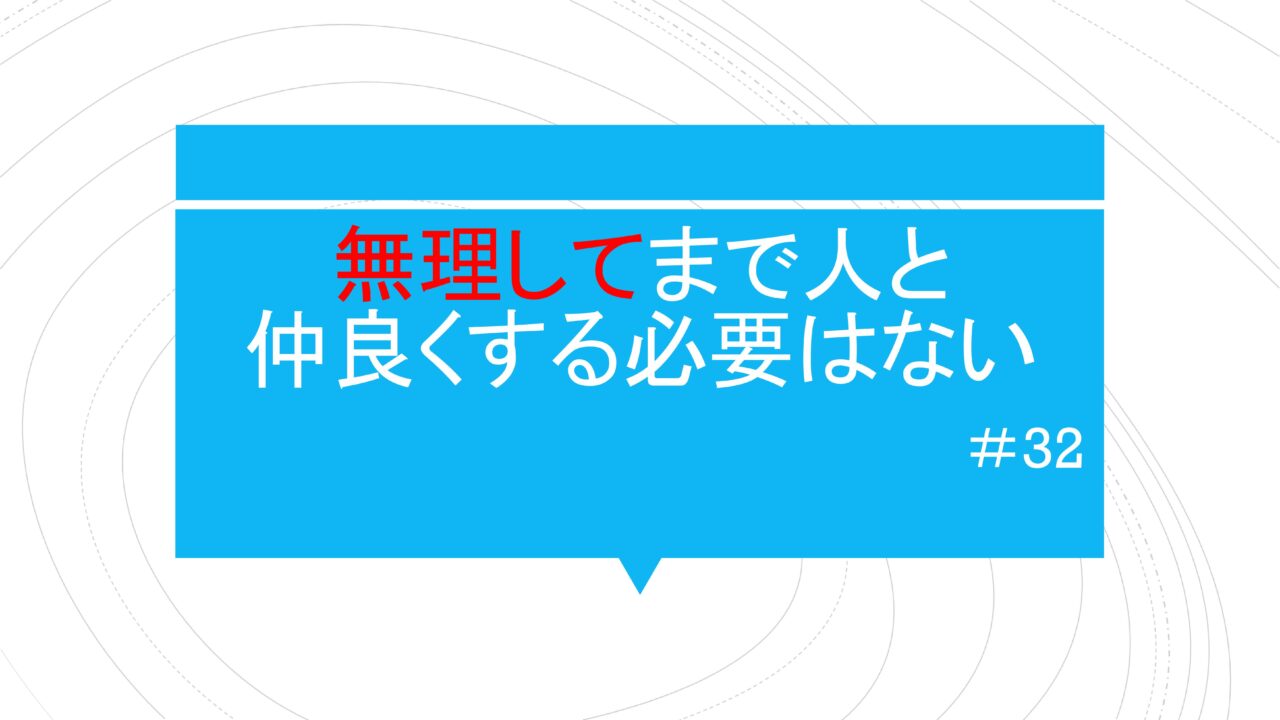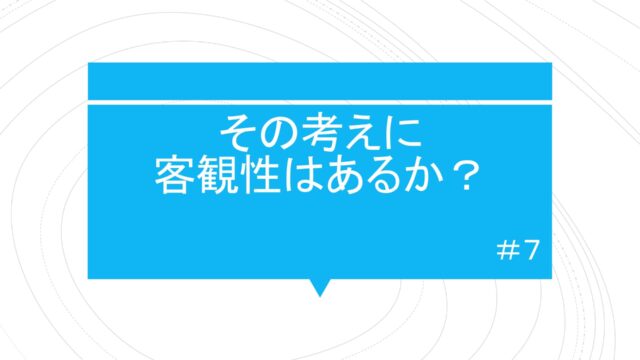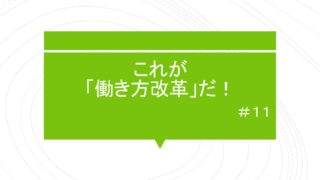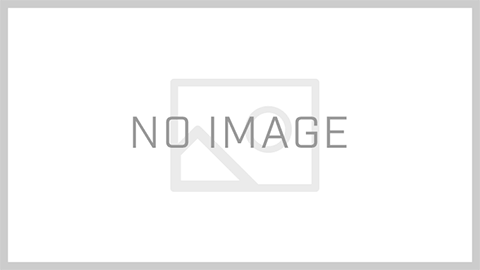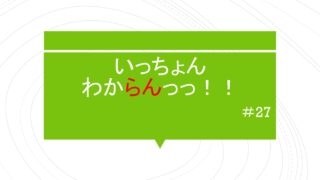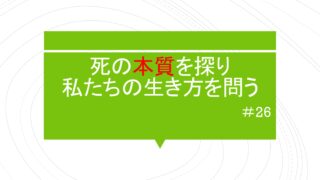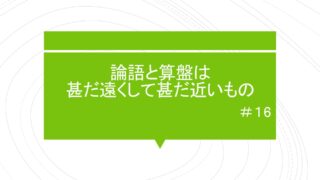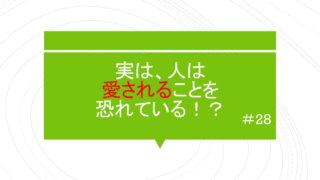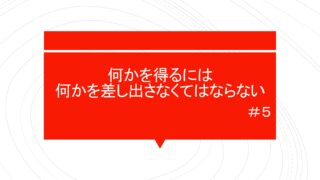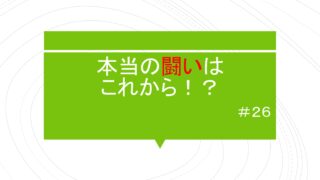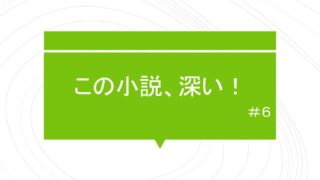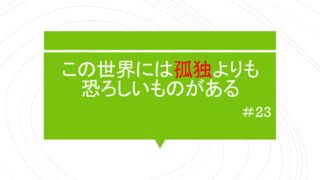うらみわびの【きょう考えたこと】第32回
はたして人間はお互いに恐れてはいけない存在なのだろうか。今回はこの問いに対して精神と身体の2つの側面からみていく。
友達100人いたら淋しくない?
「みんな仲良く」とは言われるが、それが必ずしも正しいようには思えない。「友達100人できるかな」という歌があるが、あれは真理ではないと私は考えている。あの歌が歌われたのはいつの頃だったか。それは幼児であり小学生の頃であった。まだ小さいうちは「友達100人作る」くらいの気持ちがあっていい。はじめの目標は少しポジティブすぎるくらいでもいい。
しかし、年齢を重ねていくにつれて私たちはどの人間とどの程度の距離で付き合っていくのか、ということも考えていかなければならない。大人になると様々な場面で行動の責任が自分にのしかかってくるもの。多くのものを自分一人でしょい込まなければならない。
人間のなかでもいわゆる悪人、人に害を与える人間というのは存在する。それらの人ともある程度は、表向きだけでも仲良くしなさい、と言う人がいる。おそらくその理由は、上辺だけでも仲良くしておくことで、相手からも譲歩を引き出したり、場合によっては害を被らないことになる、という点だろう。果たしてそうなのだろうか。
エネルギーバンパイアという語がある。人からエネルギーを吸い取る人々を指す。この考え方はかなり研究されているようで、いやみを言うタイプや助けを求めてくるタイプなど様々なタイプのエネルギーバンパイアに類別されているので舌を巻く。エネルギーバンパイアが示唆するのは、人間の中には避けなければならない人が存在する、ということである。
人間は自分のなかに余裕があるときにはじめて人に愛を施すことができる。反対に、自分にエネルギーが枯渇しているときには施すことはできないのである。形は施しているようでも中身がこもっていなかったり、後になって抜け殻となり、元の自分に修復できない事態に陥ってしまう。
エネルギーバンパイアと呼ばれる人たちはあらゆる手段を用いて私たちの活力を半ば無意識のうちに吸い取ってしまう。本人が意識的にやっている場合もあるし、無意識でやっている場合もある。
このような人たちと渡り合える器用な人もいるが、皆ができることではないし、そうする必要もない。エネルギーバンパイアの人たちはその人自身の内面に何らかの「もの足りなさ」がある。当人がそれを適切な方法で満たしてあげない限りは当人にとっての和解は見込めない。
つまり、人間の中にはこちらのアプローチだけでは和解できないような相手が存在するのである。そのような人たちと面と向かって無理に打ち解けようとしても骨折り損となってしまう。むしろ私たちの精神がダメージを受けてしまいかねない。
だからこそ、私たちは相手をよく観察し、適切な距離をとって接しなければならないのだ。その意味では、相手を正しく恐れなければならない。
恐怖は思考を停止させる
ここまでは、精神の面でみてきたが、ここからは身体面で見ていきたい。
これは私自らが体験してきたことである。私の祖父は暴力的な人である。何事も力で解決しようとする。厄介なのが、家にいるときは必ずアルコールが入っている、ということだ。私は幼児期から祖父に酒の肴にされた。大声で怒鳴りつけて、恐れおののいた私の顔をみてケラケラ笑うのである。5歳の時にはみぞおちに拳を食らった。階段で鉢合わせになった時のである。あの時の痛みは今日のことのように覚えている。
最近では、大きな音をたてることで気を惹こうとしている。突然、手を叩く。飲み終わった酒の缶を拳を入れて潰す。電気のスイッチは拳で押す。ドアや壁に拳を入れる・・・。私がHSP(Highly Sensitive Person=感受性の強い人)であるので大きな音に強く反応するのを楽しんでいるのだ。今思えば、祖父の暴力が私をHSPにしたのか、私は生まれつきHSPという性質を持って生まれたのかは定かではない。しかし、確実に私の祖父は拳を振るって、家庭内での強さを誇示している。
私の人生はそのまま祖父の暴力との対峙の人生でもある。20年以上暴力と向き合ってきたが、今でも祖父と対峙するときは内心ドキドキする。体が思うように動かない。臆病な犬ほどよく吠える。大きな音で気を惹くのは威勢はいいが、心は空っぽの居孤児なのだ。彼は決してヤクザではなくただのチンピラだ。頭では分かっていても体はいうことを聞かないのだ。
では、どうしたらよいか。和解か。そうではない。何が何でも逃げることだ。無視することだ。関わらないことだ。彼と友達になってみたまえ。虫の居所が悪いたびにサンドバックになるのがオチだ。だから逃げなければならない。絶対に。
遺伝子レベルの警戒心
人間はもともと狩猟民だった。当時は食料の調達が不安定で、村こそあれど、他の村からの侵略を警戒しなくてはならなかった。したがって、私たちには見知らぬ人とあったとき、まずは警戒することが遺伝子レベルで刷り込まれているように感じる。相手が自分にとって脅威とならないか判断するのである。グローバル化が進み、「みんな仲良く」の時代でもそれは変わらない。人間は多様性に富んでいる。それは生物学的にみれば、種の生存確率を上げ、各人がそれぞれの強みを持つことで社会を発展させることに寄与してきた。
一方で、人間の多様性は性格面での「良い人」、「悪い人」を生み出している。「良い人」、「悪い人」の基準は人によって異なる。当人の性格も千差万別だからだ。だからこそ、私たちは性格の合わない人とは必ずしもお近づきになる必要はない。
職場とプライベートは違う
「みんな仲良く」論者には勘違いしている点があるように思われる。それは「職場では表面上だけでもうまく付き合うんだから、いつでもそうしきゃだめ」というものだ。
しかし、それは正しいことではない。職場とプライベートは分けなければならない。職場では相手に関係なく時間給が支給される。その場で愛想よくしていれば、その対価が支払われるのだ。そう考えれば割り切れる。しかしプライベートはそうはいかない。自分の幸せを犠牲にしてはいけない。自分を幸せにしてくれる人と長く付き合うべきだ。ドライな言い方をすれば人間の取捨選択だが、これは人生の地雷の回避なのだ。
人生の厚みは友達の数という計量的なものでは測れない。そのことは心にとめておいた方がいいだろう。
今日も皆さんが幸せでありますように