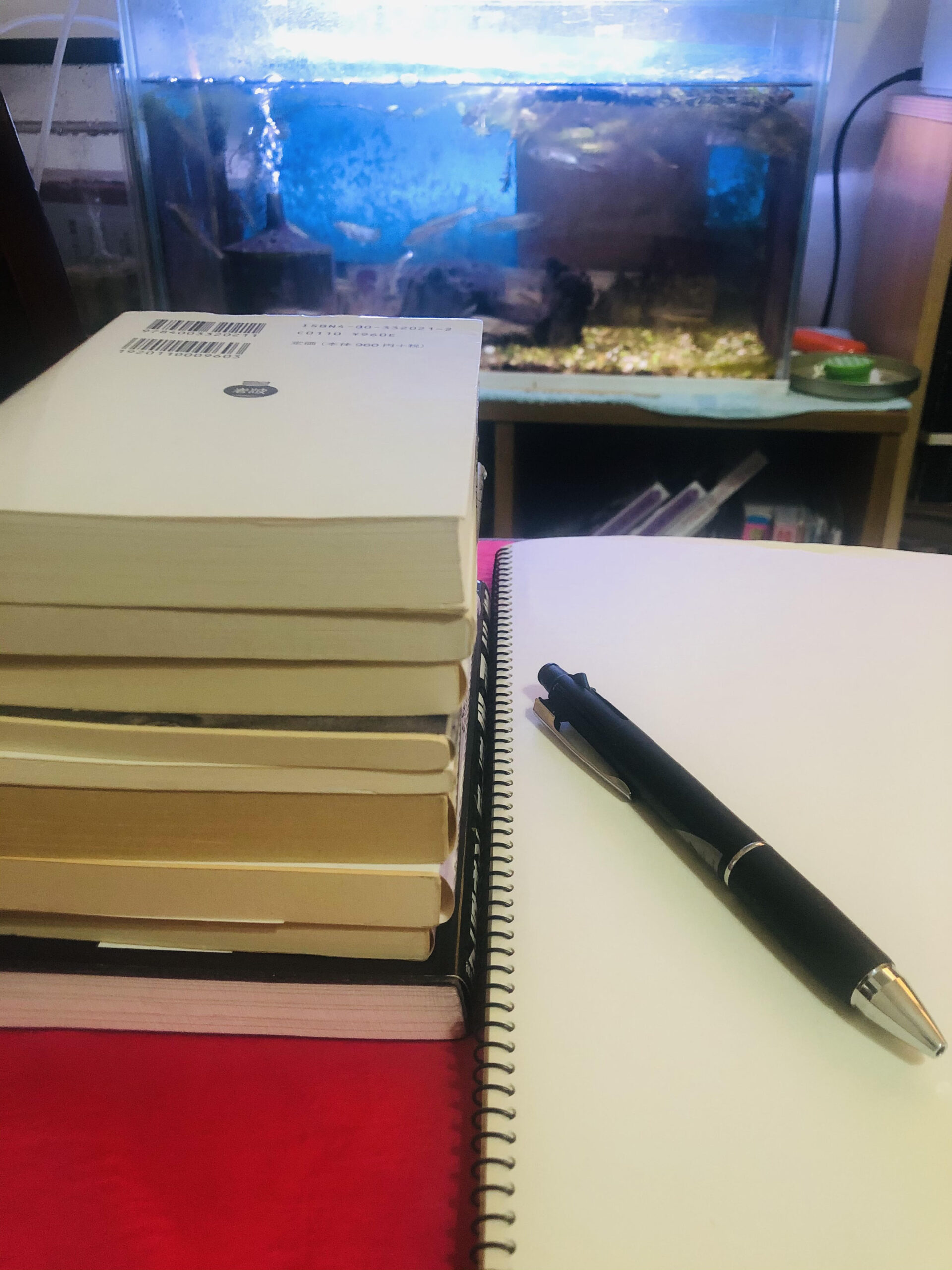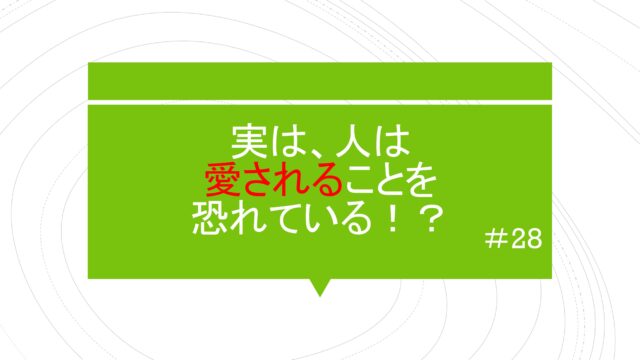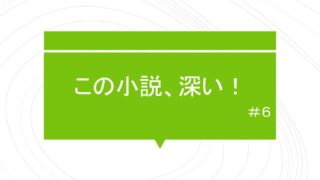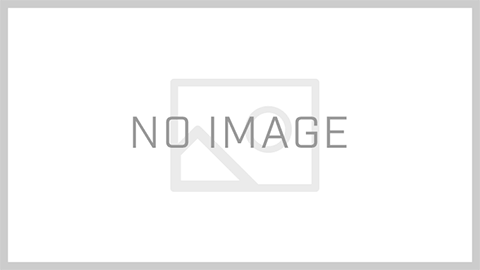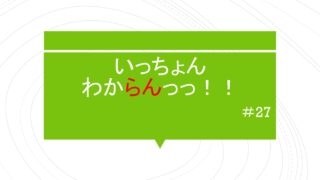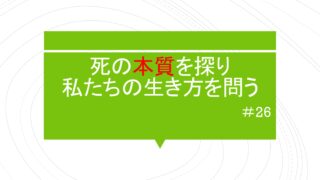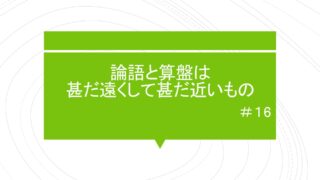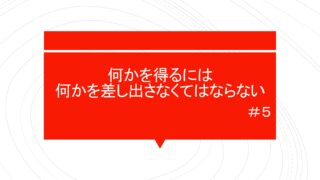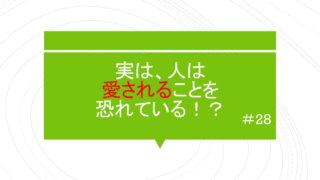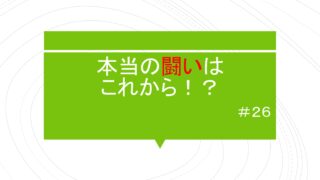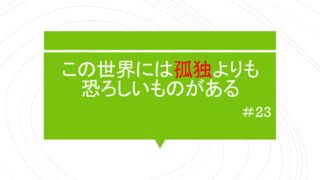うらみわびの【この本がおもしろい!】第2回
木村草太『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』
晶文社(2015)
 |
集団的自衛権はなぜ違憲なのか (犀の教室 Liberal Arts Lab) [ 木村草太 ]
|
![]()
| 勝手に評価表 | |
| ストーリー | ☆☆☆☆ |
| アクション | ☆☆☆☆ |
| 感動 | ☆ |
目次
Ⅰ 集団的自衛権はなぜ違憲なのか
- なぜ憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか
- 三つの観点から考える「日本国憲法とは何か?」
- 私を解放してくれた「日本国憲法」
Ⅱ 憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう
- 安保法制の無責任な報告書は訴訟リスクの塊である
- 政府の憲法解釈を立憲主義の原則から検証する
- 集団的自衛権に関する7・1閣議決定とは何だったのか?技術者として閣議決定を読む
- 憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう
- 衆議院の解散・総選挙は憲法のルールを厳守しているのか?
- 文言の精緻な分析から見えてくる安全保障法制の問題点
- 「ムベンベ」から憲法へつなぐセンスオブワンダー読書案内
Ⅲ 哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義 ―國分功一郎 x 木村草太―
- 哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義 哲学編 國分功一郎
- 哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義 憲法学編 木村草太
- 哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義 対話篇 國分功一郎 x 木村草太
付録 軍事権を日本国政府に付与するか否かは、国民が憲法を通じて決める ー衆院特別委員会中央公聴会 公述
あとがき
あらためて考えるときが来た
「憲法」というとなんとなく「お堅い」イメージがつきまといます。
日本国憲法は日本国民に皆が守らなければならないルールが記されている、といった感じ。
国民が生徒なら憲法は先生、といった感じかな。
ちょっと近寄りがたい。
その理由の一端はかつての大日本帝国憲法にあるのかも。
軍の統帥権を天皇に与えたり、日本が戦争を行うシステムを構築した、といってもよい。
だから憲法は強く、そして恐ろしい存在と身構えるのかもしれない。
そもそも憲法は何のためにあるのだろう。
憲法が定める条文の数々は誰に向けられたものなのだろう。
この本を読めば憲法の根本的”性格”が明らかとなってくる。
それは憲法とは権力者(政治家など)の行き過ぎた権力の行使を抑制するためにあり、その恩恵は国民に向けられている、ということだ。
他方、本書のタイトルにある「集団的自衛権」。これも「戦闘」というワードを彷彿とさせ禍々しいイメージだ。
あれは2015年。
当時は「安保法制」で国会が荒れに荒れた。
関連法案を可決しようとする与党自民党と反対派の野党議員が、それこそ拳をぶつけ合う闘いを国会で行った。
深夜にまで及ぶ審議。
当時高校生だった私は、国の平和を維持するための法案をこうも非平和的に可決させようとする与党の姿に、これからの日本の行く末を案じたのを今日のように覚えている。
あれから6年。
特に今年は世界各地で紛争が絶えない。
それは状況によっては自衛隊が集団的自衛権の名のもとに活動を行う可能性が濃くなる、ということだ。
法案自体は可決されたが、はたして集団的自衛権は合憲か違憲か。
ここにきてあらためて考える時期に来ているのではないだろうか。
そもそも安保法制とは
「安保法制」と一言にいってもその法案は多岐にわたる。
ここでいわゆる安保法制(政府は「平和安全法制」と呼ぶ)の議論の過程を簡単に振り返る。
2014年 7月1日
「新たな安全保障法制の整備のための基本方針
(国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について)
を閣議決定
→ ・政府の憲法解釈を一部変更
・集団的自衛権限定行使の一部容認(武力行使の新三要件)
2015年 5月14日
「我が国及び国際社会の平和及び安全の保障の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」
(平和安全法制整備法案)
「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」
(国際平和支援法案)
を閣議決定。
→翌15日に国会に提出。
国会ではこれらに合わせて、日本の防衛・外交・スパイテロ等の安全保障に関する情報を政府の判断で特定秘密とすることができる「特定秘密保護法」の審議も行われた。
集団的自衛権だけではない
本書はタイトルこそ「集団的自衛権」と書かれているがその内容は1つにとどまらない。
憲法そのものについて憲法学者の木村さんが分かりやすく解説してくれる。
いわば”憲法の教科書”だ。
例えば憲法解釈はなぜ必要なのか。
それは自分の思考に陥らないためのストッパーである、と木村さんはいう。
何よりも木村さんは物事を客観的に見る目に長けている。
彼の説は力強い。
それは論拠が明確でゆるぎないからである。
独りよがりではなく多角的な視点から憲法を安全保障を考えている。
本書は、いわば木村氏の客観的論理ショーだ。
憲法改正については安保法制の審議と並行して議論が加熱していったように感じる。
ここで憲法改正=集団的自衛権の容認・自衛隊の明記 と捉えるとドツボにはまる、と考える。
憲法が定めるのは権力者への制限であり、自衛権についての項目・解釈はその一部でしかない。
憲法改正の議論のなかに集団的自衛権の議題は含まれるが、集団的自衛権の行使容認が憲法改正論議の全てではない、というところに注意が必要である。
なぜ憲法改正か
ここまで集団的自衛権の行使容認、についてが主なテーマだったが、憲法そのものを考えると集団的自衛権は議論の一つに過ぎない。
もっと広く”憲法改正”についても感がる必要がある。
近年、憲法改正の熱が高まってきている。
そもそも今の日本国憲法は1947年に施行されてから一度も改正されていない。
「これでいいのか」
「いや、これでいいのだ」
様々な意見がある。
安倍前総理が憲法改正に積極的だったことも議論を活発化させる要因になった。
では、なぜ憲法改正が必要なのだろうか。
集団的自衛権と自衛隊
選挙改革
教育、デジタル
それは以上のような様々なジャンルで憲法制定時と現在とで社会の状況が目まぐるしく変化していることが挙げられる。
例えば「自衛隊」については近年の、そしてこれからの世界情勢を鑑みて、そもそも憲法に規定がなく、その活動が「違憲」とは判断されかねない状況を打破したい。
国会では資料のデジタル化が進んでいる。デジタルには脆弱性も存在し、文書管理や各省庁のデジタルの扱い方も議論の的となろう。
つまり、憲法で定められたことの前提条件が変化していることがあり、時代に合わせて憲法の条文を改正し、しっかりとカバーしていこうという姿勢だ。
熱き議論の中で
憲法は国の根幹を成すといってもいい。議論はときに「賛成」、「反対」を通り越して感情的になることがある。その危険さを木村氏は指摘する。
憲法論が必要となるときは、合理的な議論が困難となっているときだ。だからこそ、憲法という形式的な枠組みによって、権力者の行動を制限することに意味がある。
木村草太『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』
晶文社(2015)
p.273
憲法を考えるとき、私たちは”今”をどうしても考えてしまいがちである。
しかしながら、憲法にはそれぞれ制定・改定に至るまでの歴史がある。
かつて無秩序の状態から皆をまとめる強い権力者があらわれ、後に権力者の強権的政治への批判・反省から権力者の行動を縛る法の必要性が生まれた。その中身は時代の流れ、過去の政治からの反省からアップデートされていく。それが憲法の歴史である、と考える。
国によって憲法の中身は異なるが、その目指すべきは同じである。国民の幸せであり、国家の正常な運営である。
その憲法の性格を理解したうえで今を、そして未来を見据えた法整備の議論が欠かせない。
憲法論だけではない
本書のブレイクコーナー的な存在、「『ムベンベ』から憲法へつなぐセンスオブワンダー読書案内」の項もおもしろい。
憲法学者として日々、たくさんの本を読む木村氏。その原点となる思考とはどのようなものなのか。
「『センスオブワンダーを身につけるための10冊』木村草太選」にも注目。
【紙の書籍】
 |
集団的自衛権はなぜ違憲なのか (犀の教室 Liberal Arts Lab) [ 木村草太 ]
|
【電子書籍】![]()
 |
価格:1,100円 |
![]()
#RPG #SF #いじめ #うつ病 #アニメ #エッセイ #オクトパストラベラー #ゲーム #スクエニ #ニーチェ #ファイナルファンタジー #ファイナルファンタジー4 #ファイナルファンタジー4 #フィクション #メンタルヘルス #リモート旅行 #京都アニメーション #人間関係 #人間関係の悩み #働き方 #単行本 #哲学 #夏 #孔子 #学校 #学習 #家庭 #小説 #幸せ #恋愛 #憲法 #憲法改正 #戦争 #政治 #教育 #文庫 #木村草太 #本が好き #正しさ #社会 #組織 #自分磨き #自殺 #適応障害 #集団的自衛権