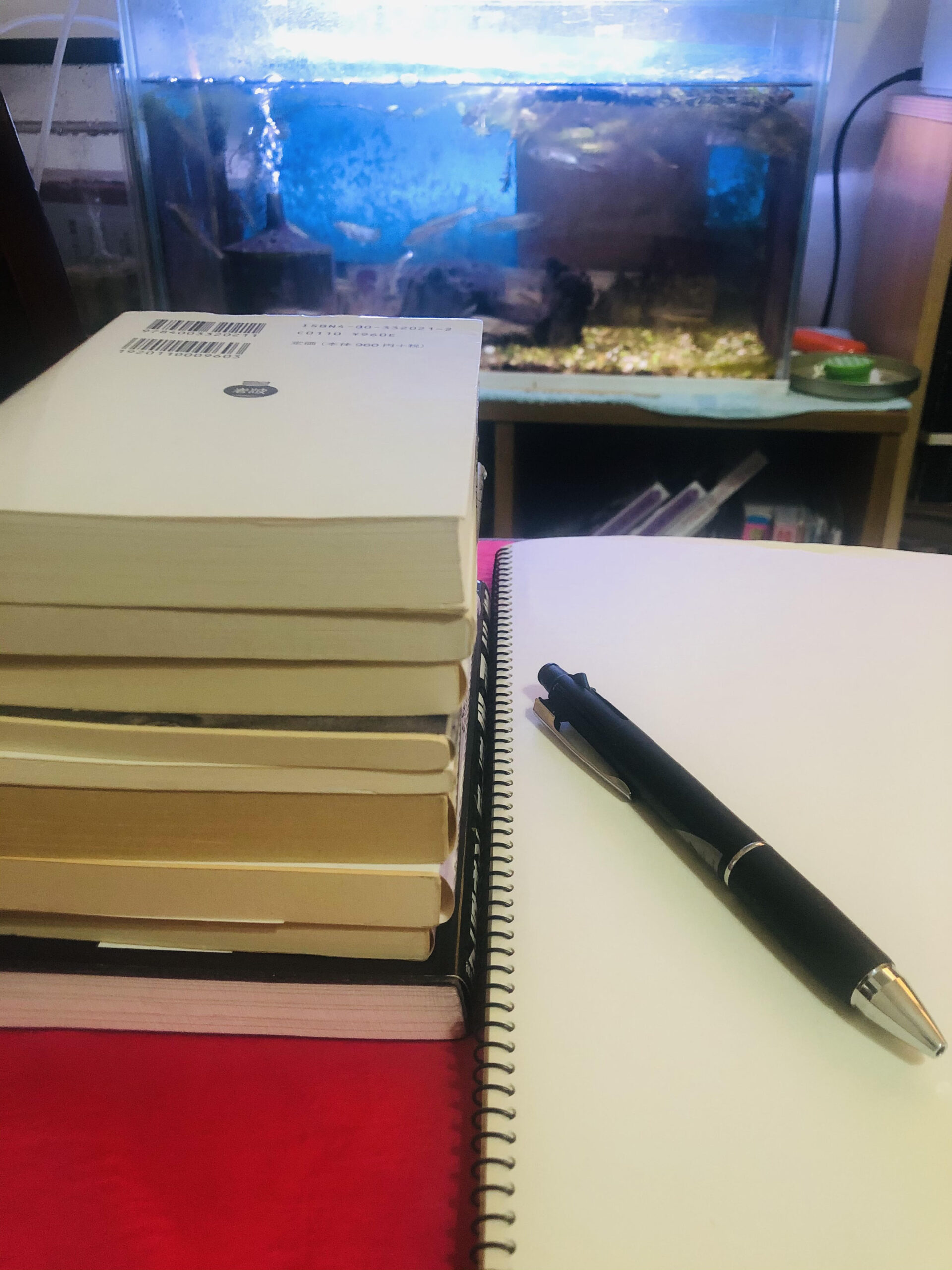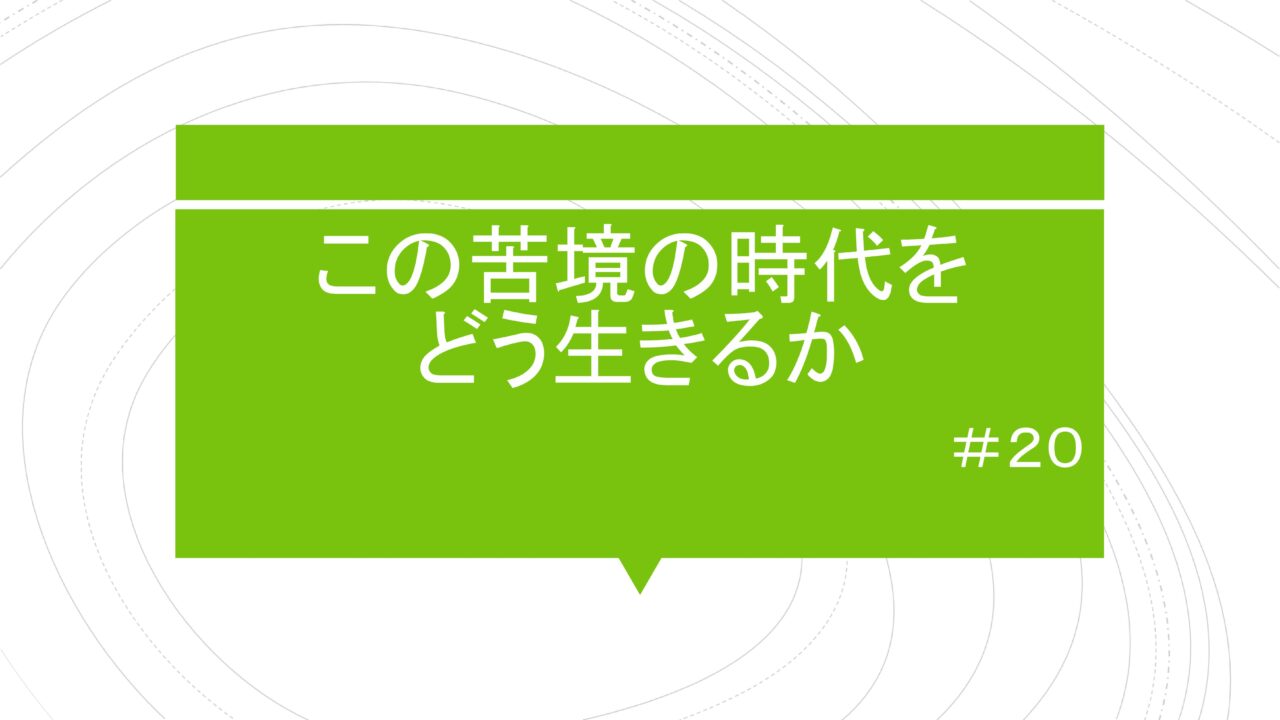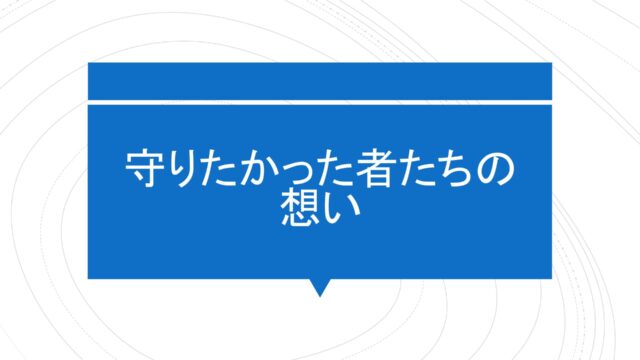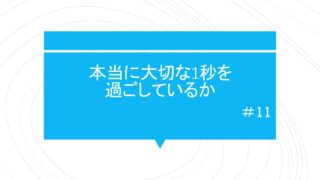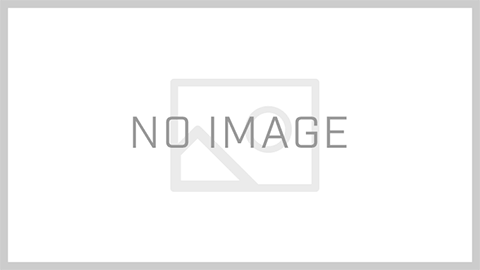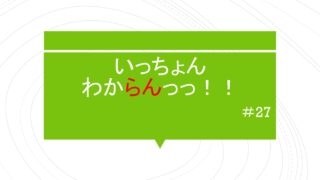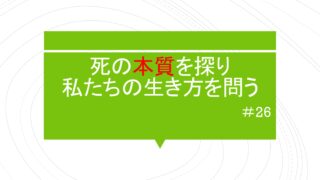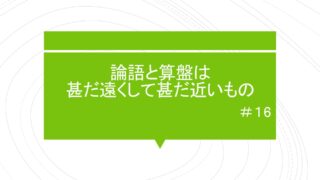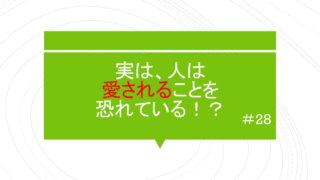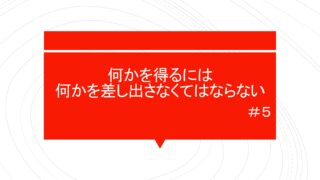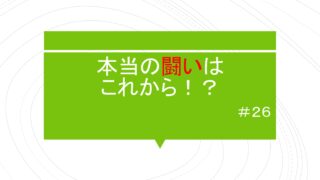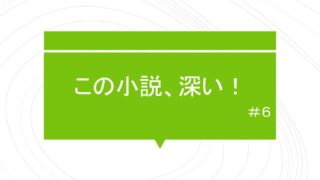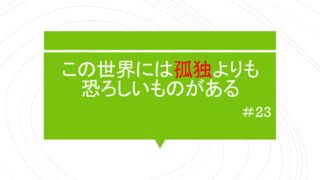うらみわびの【この本がおもしろい!】第20回
 |
|
働き方5.0 これからの世界をつくる仲間たちへ (小学館新書) [ 落合 陽一 ] 価格:902円 |
![]()
この本の著者、落合陽一さんは筑波大学の准教授であり、メディアアーティストという異色の経歴をもっています。テレビのニュース番組のコメンテーターも務めており、顔だけでも見たことのある人は多いと思います。
「『社会の前提』は覆された。新たな世界の景色と展望を共有したい」という著者からのメッセージに現れているように、この本は、コンピュータが登場してからモノの製造から働き方まで、社会に現在進行形で起きている変化を客観的に捉え、これからの生き方、働き方を提案しています。コロナウイルスの伝染によって世界だけでなく、目下の日本社会は様々な面での変化を余儀なくしています。今の社会に生きづらさを感じている人、これからの人生の進路を描き切れない人、これからの社会に通用する子供を育てたい人、そんな人に薦めたい本です。
これからは「幸福」がベース
本書は単なる自己啓発本ではありません。まずは、コンピュータの登場が社会をどのように変化させたか、という変遷を追いながら、今後の社会の変化、求められる人材等々について定義していきます。
ただ、そこで終わらないのがこの本です! この本が追い求めているのは、単なる人々の社会における「成功」だけでなく、その先の「幸福」の在り方であるのです。
私自身、現在の日本社会には、仕事の「成果」や他者からの「名声」にこだわるあまり、自らの「幸福」を犠牲にしている人が多いのではないかと危惧しています。コンピュータの登場、ネット社会の進化によって、働き方は変化し、求められる人材も変化しています。それを踏まえて、これからは仕事と幸福の両立、というより「共存」の社会が求められると思うのです。著者である落合さんはこの本を通して、幸福をベースとした、社会で求められる人材になることを私たちに提示しているのです。
研究に必要な体力
本書において、「勉強」と「研究」の違いが示されている。つまり、勉強とは、誰かの過去の成功、発見を追体験することであり、研究は、誰も発見していない新たなものを作り上げることである、としている。この両者の違いは重要であると落合さんは言う。
私もそのように考える。というのも私自身、学生時代は学校の勉強を愚直にこなしていたが、大学を卒業しても、結果として、社会に通用する人材となったのか、と聞かれると自信がない。ここでは学校教育の在り方も問わなければならない。
現行の学校教育の在り方に疑問をもっている人は多いのではないのだろうか。具体的には、「今の英語教育では、国際社会に通用しない」、「中学から6年、英語を勉強してもまったく英語を話せるようにならない」といったものや「中学、高校の授業が入試対策に変容している」といった批判だ。
私は短い間であったが、高校の教壇に立って、このようなことを常に考えていた。「高校教育はどうあるべきか」と。つまるところ、まだ明確な答えは出ていない。そのなかで、通過点ながら、今の私の考えを述べていきたい。
学校は「勉強」をする場所であり、かつ「研究」の具体的なアプローチを学ぶ場所であると考える。「研究」はこれまでにないものを新たに生み出す、ものであることは本書でも述べられていることであるが、この「研究」の基礎となるのが知識である。そして知識を学ぶのが学習、つまり学校教育でいうところの勉強である。研究には勉強が必要なのだ。
余談であるが、私は「勉強」という言葉が好きではない。この言葉には一種の強制力が働いているからだ。いやいやながらに人にやらされる学習が勉強なのだ。学習は自主的になされるべきである。なぜならその先にある研究は私たちに多量の探求的体力を要求するからである。興味のないことを研究など到底できない。
一方で、私たちは知識において何が必要で、何が不要かを全て自分で判断できるとは到底思えない。10のうち1が自分に必要だとして、1だけを学べばよい、とはならないだろう。その1が本当に必要だと分かるためには最低でも他の4を学び、両者を比較しなければ、その1が真の意味において自らにとって重要であるとは解らないだろう。政治についてだと、憲法9条改正の議題ひとつをとっても、単に現状の日本と世界の情勢を考えるだけでは足りない。これには日本の江戸時代の鎖国から明治維新、太平洋戦争を通して、日本がどのようなことを考え、経験してきたのかを丁寧に読み解いていかなければ、論理的な意見を提示できないだろう。つまり政治的解釈にも歴史的知識が必要とされるのである。
現在、あらゆる学習範囲が細分化され、結果として中高生が学ぶべき内容も増えている。参考までに、過去10年で中学生の教科書のページ数は30%、過去8年で高校生の教科書のページ数は16%増加している。(参照:http://www.textbook.or.jp/publications/data/18tb_issue.pdf)
したがって、中高生のなかには、今、自分が受けている授業の内容は自分には必要のないものだ、と考える学生が出てくるのも無理はない。私にも経験がある。ある生徒が私のところに来て、「こんなに延々と英文の訳を考えさせられてつまらない。そもそも自分には英語は必要ない。」と言ってきた。私は「いつか必要になるかもしれないから、今はしっかりと勉強しなさい」と答えたが、なんとも自信のない答えになってしまった。
しかし、前述したように、学校は勉強をするための場所である。そして今後の研究には体力が必要だ。これは野球でいうところの筋トレやノックにあたるのが学校教育だ。プロの試合を見ているだけでは、野球はうまくはならない。強いて言えば、学校で様々な教科を学ばせるのは、様々な視点からの研究のアプローチを知るためである。その本質は研究課程の追体験であり、そこで得た教科の知識は副産物でしかない、と捉えたほうが合理的かもしれない。
したがって、私は現在の中高生にはこう言いたい。「今のうちにたくさんのことを学習し、興味の根を張っておいた方がいい。その根は今後の自分を育てる養分を与えてくれるはずである」と。厳しいようであるが、はじめのうちは(特に)学問に好き嫌いは禁物だ」
「組み合わせ」が唯一無二をつくる
学問における好き嫌いがいけないのには、もうひとつの理由がある。それが、落合さんが本書でも触れていた暗黙知の存在である。
これからの社会で価値のある人材となるには、この暗黙知が欠かせない。この世界はある意味ではかなり研究されつくしている。雇用の面においても、あらゆるホワイトカラーの仕事が機械に置き換わっているからだ。
したがって、学校で習ったことや、ネットですぐに答えが見つかるような、単一的な知識では魅力的な人材にはなれない。暗黙知は言い換えれば、知識の組み合わせである。ひとつひとつの知識は単一的でも、それが他の人が思いもよらない組み合わせをもったなら、それはあなただけの知識となる。それはオリジナリティーにあふれ、とても魅力的な知識である。
ダブルライセンスという言葉が世に出回って久しいが、これも広い意味では暗黙知の一例と言えるだろう。この社会ではすでに一つの資格だけでは心もとない。同じ資格をもった他の人と差別化ができないからだ。そこで他の資格も合わせて所持し、差別化を図ろうとするのだ。(税理士と社会保険労務士の2つの資格をもつように)
暗黙知は知識の組み合わせの集合体だ。その個々の知識は広い分野にまたがればまたがるほど他との差別化が図れる。だからこそ、知識には好き嫌いがないほうがよいのだ。
ビギナーズマインドという言葉がある。初心者のほうが、その道の専門家よりも新しい視点でよい発見ができる、というものである。これは本書において引用された金出武雄先生の『素人のように考え、玄人として実行する』という著書名にも表れていることだろう。
 |
|
【中古】 素人のように考え、玄人として実行する 問題解決のメタ技術 / 金出 武雄 / PHP研究所 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】 価格:2,049円 |
読書の価値
暗黙知を多く持っている人がこれからの社会で必要とされるなか、読書の価値が再認識されるように感じる。読書は自分がこれまで持っていなかった新たな知識を供給する。一つの区切りとして社会人として働く前にどれだけの本を読んきたか、がその人のポテンシャルを計るものさしとなるだろう。
読書には2種類がある。お腹を満たす読書と体をつくる読書だ。お腹を満たす読書は、自分が興味を持った分野(複数あるのが望ましい)の本を読むことだ。自分の好きな分野を決めて、それに絞った読書をすることで、自分の知識を確固としたものにするのである。
一方、体をつくる読書は、あえて自分がこれまで興味を抱かなかった分野の本を読んでみることである。これはちょうど牛乳が嫌いでも骨を作るために毎日コップ一杯の牛乳を飲むように、体、ここでは知識のバランスを整える為に読む本が必要である、ということだ。体をつくる読書をすることで、知識の裾野は一気に広がる。そして異分野の知識を自分の得意分野に織り交ぜることで、あなたの論に説得力が格段と増すことだろう。その論が心に刺さる聞き手の数も増える。これは野球でいえば、バッターボックスに入ったときに、自分が打ち返せる球種やコースを明確にしておく。これがお腹を満たす読書。次なる体をつくる読書は、自分の得意なコースに入ってこない球を打ち返せるようにミートの幅を広げることである。こうすることでヒットの率を上げていくというわけだ。
最後に
今回、初めて落合さんの著書を読んだ。以前より、その時代の先端をいく理論を展開している姿に尊敬の念があったし、私の友人にも、教育者で落合さんの考えを好意的に受け止め、自らの教育に活かしている人もいる。私としては、どの道でも成功を収めるためには我慢の時期が必ずある、と考えている。したがって、現行のいわゆる詰込み型の教育に対して必ずしも否定的な見方はしていないが、教育課程のスリム化は必要であろう。いずれにせよアウトプットがさらに必要である。人々、とりわけ若い人たちが自らの考えを発信し、共有できる場を多く作ることがこれからの個人の成長、ひいては社会の躍進につながると確信している。