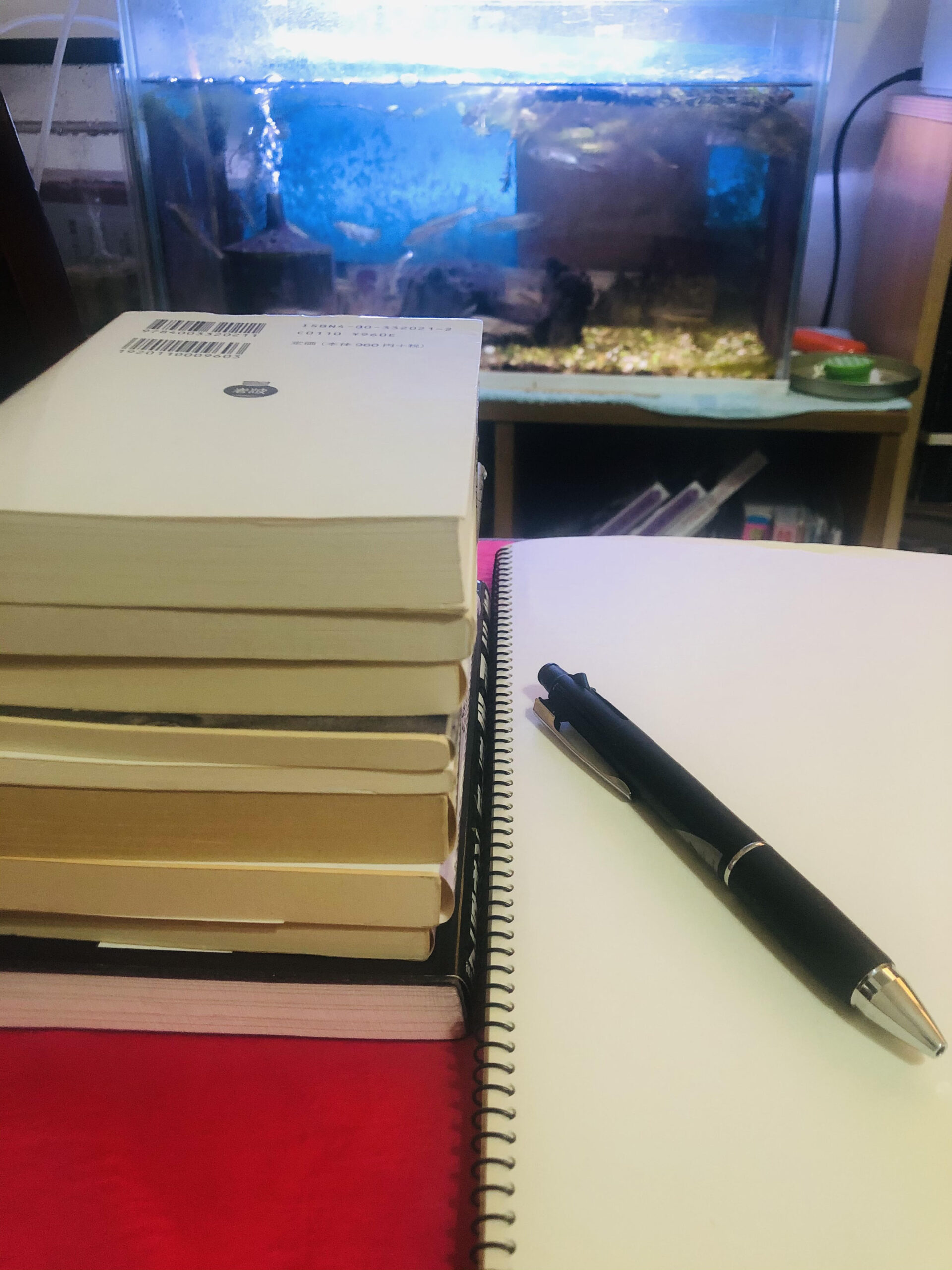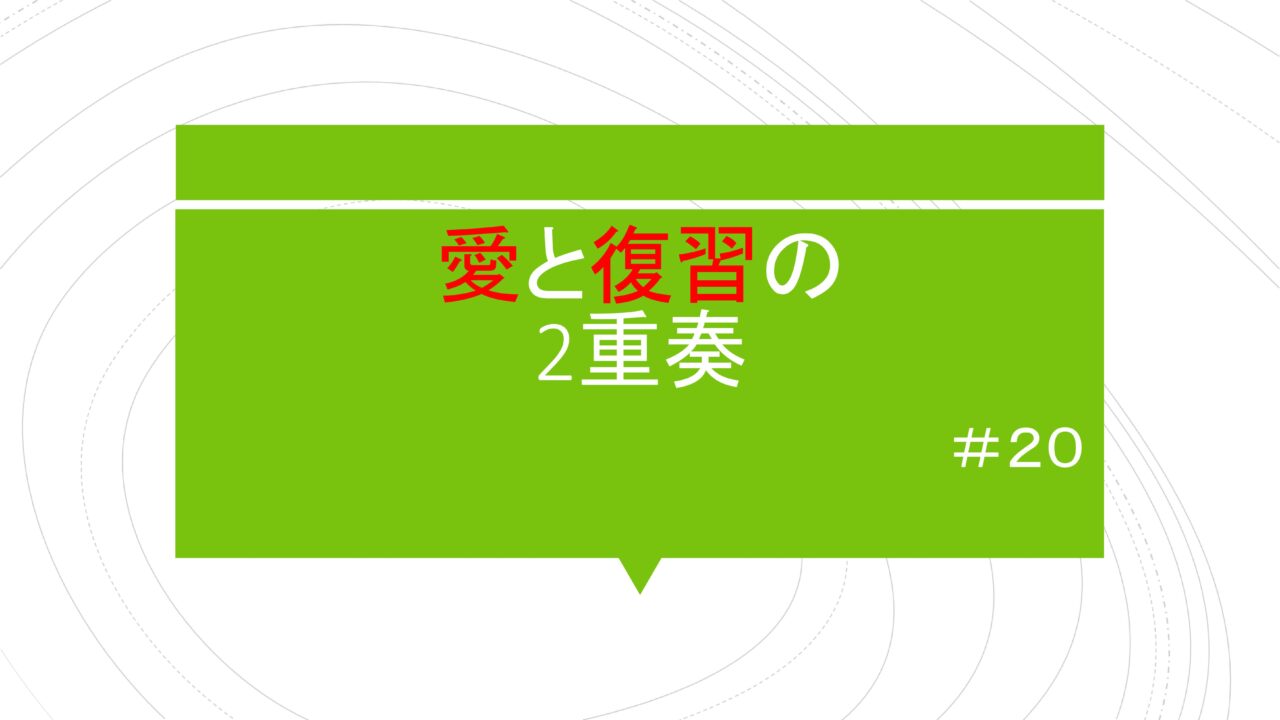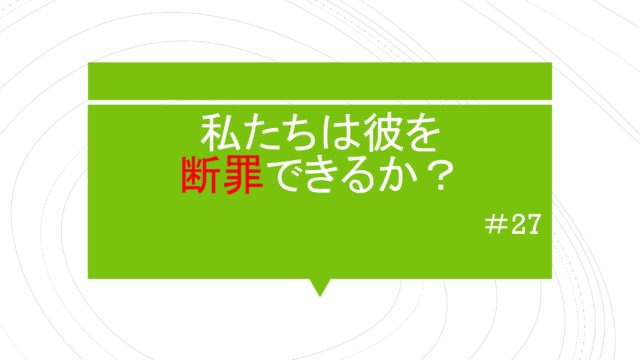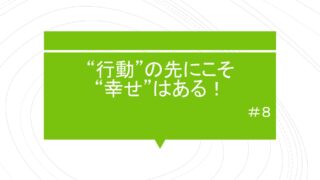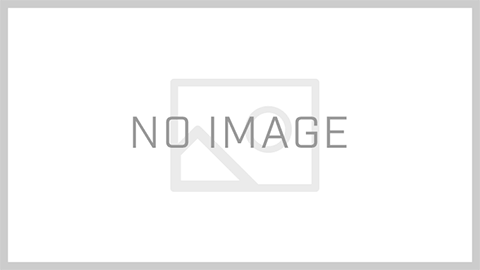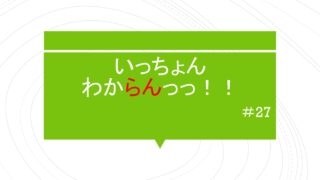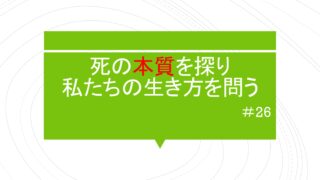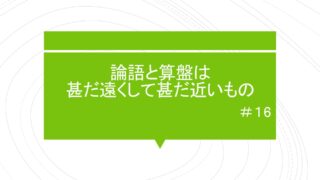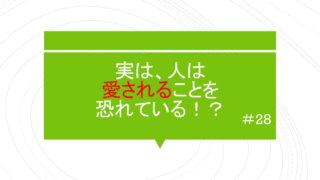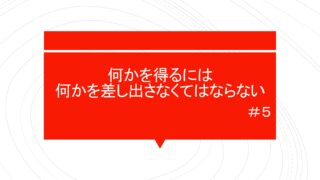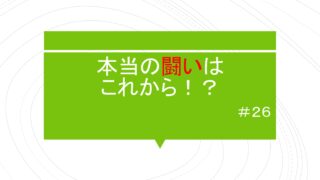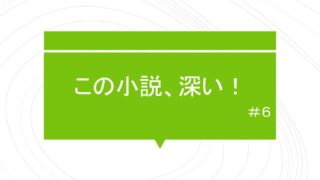うらみわびの【この本がおもしろい!】第20回
生きていると様々な場面で他者と衝突する場面があります。それに対してこちらから反撃するべきでしょうか。または、自らの意見をぶつけるべきでしょうか。
もちろん場面によって答えは異なるでしょう。しかし、もし自らが深く傷つけられたとしたら、あなたは我慢できるでしょうか。
我慢か報復か
無視か挑戦か
そんな人間関係における悩ましいスタンスの狭間に起こる議論、この小説はそれを問いかけているように感じます。
 |
|
残像 上 (手から手へ 三浦綾子記念文学館復刊シリーズ 5) [ 三浦綾子 ] 価格:1,760円 |
![]()
 |
|
残像 下 (手から手へ 三浦綾子記念文学館復刊シリーズ 5) [ 三浦綾子 ] 価格:1,760円 |
![]()
| 勝手に評価表 | |
|---|---|
| 内容 | ★★★☆☆ |
| 難解度 | ★★☆☆☆ |
| 価格 | ★★☆☆☆ |
どんな話
今野弘子は3人兄弟の末っ子。
北海道の放送会社に勤めている。
仕事の方は順調。
しかし、弘子は兄である栄介の存在に頭を悩ませてきた。
定職につかず、うちでは我が物顔で振舞う栄介。
栄介に対して放任的な父親と母親。
そんな最中、真木家に紀美子と名乗る女性が訪ねてくる。
栄介の子どもを身ごもっており、どうしても産みたい、という紀美子。
「私の子どもだとでもいう証拠があるんですかね」と突っぱねる栄介。
そして数日後、紀美子は自殺する。
紀美子の自殺に悲しむ父、市次郎。栄介への恨みに燃える紀美子の兄、治。
弘子は栄介を中心としたドロドロの人間関係に翻弄されていく。
罪と罰
親と子
正義とプライド
深雪の北海道における
様々な感情が渦巻く人間劇。
主な登場人物
【真木家】
・弘子
真木家の長女で3人兄弟の末っ子。
仕事熱心で真面目な性格。兄の栄介の存在を心配し悩んでいる。
・栄介
真木家の長男。自由奔放な性格。異性に目がなく、度々問題を起こしている。
厄介ごとからは逃げる性格。
・不二夫
真木家の次男。寡黙で多くを語らないが、優しく頼れる性格。
栄介に対してはどうしようもない、と割り切った考えを持っている。
・洋吉
真木家の主。その道数十年のベテラン教師で中学校の校長を務めている。
輝かしい功績とは裏腹に長男の栄介の存在には頭を悩ませている。
・勝江
洋吉の妻。非情で他者に無関心。
そんな性格から栄介の言動に対しても特段の反応を示さない。
【西井家】
・紀美子
栄介の交際相手を名乗る女性。栄介との間の子どもを産みたいと直談判に行くが、栄介に拒絶され、後日自殺する。
・治
紀美子の兄。自殺した妹の無念を晴らすため、栄介と真木家に対する報復を模索する。
・市次郎
紀美子の父。
苦しんだ末に自殺した娘を悲しむが、真木家への報復に対しては煮え切らない態度。
無口な不二夫
”聴く”という姿勢
本作は主人公である弘子の視点で物語が進む。しかし、登場人物の感情としては弘子は真面目な分、優柔不断で自らのスタンスに迷いが感じられる。
一方で、その他の登場人物、例えば弘子を除く真木家の人物の性格はある程度定まっている。そして、自らを除いた真木家の人物が自らとあまりにも異なった人間観をもっていることに弘子は驚愕するのである。
私が一番印象深い人物は次男の不二夫である。不二夫は銀行員で仕事はきっちりとこなす真面目な男である。
その性格は寡黙で多くを語らない。物語を読み進めていくと、そんな不二夫の寡黙さの原因が垣間見える。それは、他者を傷つけまい、とする姿勢である。換言すれば、他者の思想に土足で踏み込むことをためらう心を持っている。
「僕は……人が苦手なんです」
不二夫は自らが何かを言うことで他者との間にいらぬ亀裂が入ることを恐れている。
そんな不二夫とは正反対に自らの意見をはっきり言う女性がいる。それが地方から単身移住してきた画家の摩理である。
「黙りこくっていたら、人は傷つかないと思うのね。不二夫さんって。
あなたは、だまっていてわたしを傷つけたわ。」
「傷つけまいとすることも、あなたのようになっては傲慢よ。
人間は弱いんですもの。傷つきやすいものよ。
傷つけまいとして、人とろくに口をきかない存在なんて、目ざわりよ。
至らぬために傷つけ合うことはあっても、それは仕方がないんじゃない?」
――これは私にとってよく経験する議論であるし、社会でもそうではないだろうか。
つまり、自らの意見をオープンに言うべきか・言わぬべきか。
もちろん、場合によっては言うべき時もあろう。会議で意見を封印することは議論の土壌を形成できなくなる面で損失が大きい。反対に若手社員が出しゃばるんじゃない、という意見には賛同しかねる。意見とは多すぎるくらいがちょうどいい。そのなかから取捨選択、熟考、深化を重ね、洗練されていくものが意見である。
他方、自らの意見を封印するべき場面もある。私は飲み会で多く経験する。それは私情をあえて挟まず、相手の話を”聴くに徹する姿勢”である。カラオケでもそうであるが、仲間みんなで集まっているのに自らの歌を聞いてくれない、スマホをいじっている、というのはどうしてもシラケてしまう。やっぱり自分の声を聴いてほしい、という気持ちは心の中にある。
であるならば、たわいもない話でも、偏見の混じる話でも、飲み会の場なら、仲間内のカラオケなら、まずは聴く、ということくらいしてもいいのではないか。
ここでの目的はお互いの気分の高揚にある。議論で結果を出すことではない。だからこそ、相手の意見にあえて反論する必要を私は感じない。これが飲み会で寡黙な男としての私の流儀である。
念のため申し上げるが、私はいつでも無口なわけではない。相手の話を引きだす質問は心掛けているし、メンツによっては私がメインで話すこともある。要はバランスである。仮に私の話をまともに聞く気のない人ならば、私はあえて話そうとは思わない。
”怨み”の矛先
加えて先ほどの摩理のセリフの中の「至らぬために傷つけ合うことはあっても、それは仕方がない」というところは気にかかる。
自殺した紀美子の兄、治は栄介と真木家に執拗な恨みをもっている。治は言う、「目には目を」。
栄介が紀美子に対して取った態度と行動は決して許されるものではない。治が恨みを持つことは自然なことともとれる。これは治の感情の問題だ。
他方、真木家、殊に栄介以外の人間にどこまで非があるだろうか。私はほとんどない、と考える。
これは実際でも起こり得る議論である。つまり、ある凶悪事件の犯人によって多くの人が命を落とした。そして犯人も命を絶った。こうしたとき、世間の批判の矛先は残された犯人の親族に及ぶことがある。「親の監督不行き届き」やら「教育不足」やらといった理由からである。
私はこのような論調は的を外れている、というほかない。
なぜなら、人の感情・思想などというものはその人個人のものである、からだ。親や親族のものではなく、ましてや他者のものではない。
であるから、「親の監督」や「教育」などというものには限界がある、ということは事実だろう。もしかしたら世間の大半はこの事実に気付いているのではないか。ただ、自らの怒りの矛先が仕方なく親族に向いている、という状況である。これに対して私は半ば同情するので、その道理の通らないところは批判するが、その行動自体を否定するまでにはいかない。
他方、程度の差はあれ、人々からの批判にさらされることは多々ある。これは仕方のないことである。それだけ人々の思想は多様化しているからである。
同時に私たちには何を信じ、何を実行するか、についての”自由”、”裁量”がゆだねられている。
つまり、私たちは誰と付き合い、誰と付き合わぬのか、について自らが決める権利がある。
孔子は言う。
「怨みをかくしてその人と友だちになるのは左丘明(聡明な先人たち)は恥とした。丘(私)もやはり恥とする」
これが私なりの摩理の意見に対する返答である。
 |
|
価格:1,177円 |
![]()
勝江の無関心
『残像』では様々な登場人物の”心情”が渦巻く。真木家の女房、勝江の存在も独特だ。
彼女は栄介に対して放任主義を貫いている。そうでなくとも、喜怒哀楽というものが欠如しているように感じられる。
本書を読み進めるうちに勝江の感情の裏側にあるものに気付いていく。ここがまたおもしろい。
遺伝
犯罪の遺伝子
栄介の悪行に対し、同じ家族として恥ずかしい想いをもつ弘子。彼女は西井家からの批判の矢面にも立たされる。
そして彼女は想うのである。もしかしたら、私の家族の中に犯罪者の遺伝子があるのではないだろうか、と。
――ここまでくると荒唐無稽なように感じるが、そうともいいきれない、と感じることもある。
”遺伝”ということを考えると、人間は有性生殖を繰り返す。これは自らと全く同じコピーをつくりだす無性生殖とは異なる方法だ。
有性生殖によって生み出された子供は親とまったく同じになならない。それでも親と全く異なる性格にはならない。なぜなら、母親と父親の遺伝子を半分ずつ受け継ぐからである。
遺伝子には様々な情報が集約されている。
もし、”犯罪者の遺伝子”なるものが情報として存在しているのだとすれば、どうだろうか。
2014年には欧米の研究チームが受刑者の遺伝子を解明して、暴力犯罪に関係する遺伝子を特定した、という研究結果も出されている。(関連資料1)
なかには両親のどちらにも似ていない、という子供もいるだろう。そうした場合、両親のどちらかかの両親、つまり祖父母に似ている、というケースがある。 いわゆる”隔世遺伝”というものだ。
弘子はこのようなあらゆる遺伝のパターンを考え、いったい両親のどちらの遺伝子が犯罪者の遺伝子なのか、はたまた自らにも犯罪者の遺伝子があるのではないだろうか、と想像し嫌悪する。
――繰り返すが、このような考え方は心理学や犯罪学においてはある程度有意義なものである、と思うが、実際においては荒唐無稽である、と考える。やはり育ちが大切だ。
遺伝という観点からいえば、有性生殖はむしろ生物の多様性を担保している。親の完全なコピーではないから子どもたちはみな、異なる性格・考え方をもつ。そしてこれが育ちの環境とも交差して無限の可能性を私たちに提供するのである。
父親として、教師として
真木家の主人、洋吉にも個人的な悩みがあった。無論、長男の栄介のことであるが、それは真木家の主としてのそして聖職である教師としての恥の心である。
興味深いのは洋吉が一家の主としてよりも、教師として周りから白い目で見られることにおびえていることである。
ここに周りの目を気にしてしまう人間の性のようなものを感じる。
そんな洋吉の心理を浮き彫りにする事件が勃発して……
「人間の心理を浮き彫りにする小説」というのが一言の感想でしょうか。
筆者、三浦綾子氏の筆術に驚くばかりです。
今日も皆さんが幸せでありますように