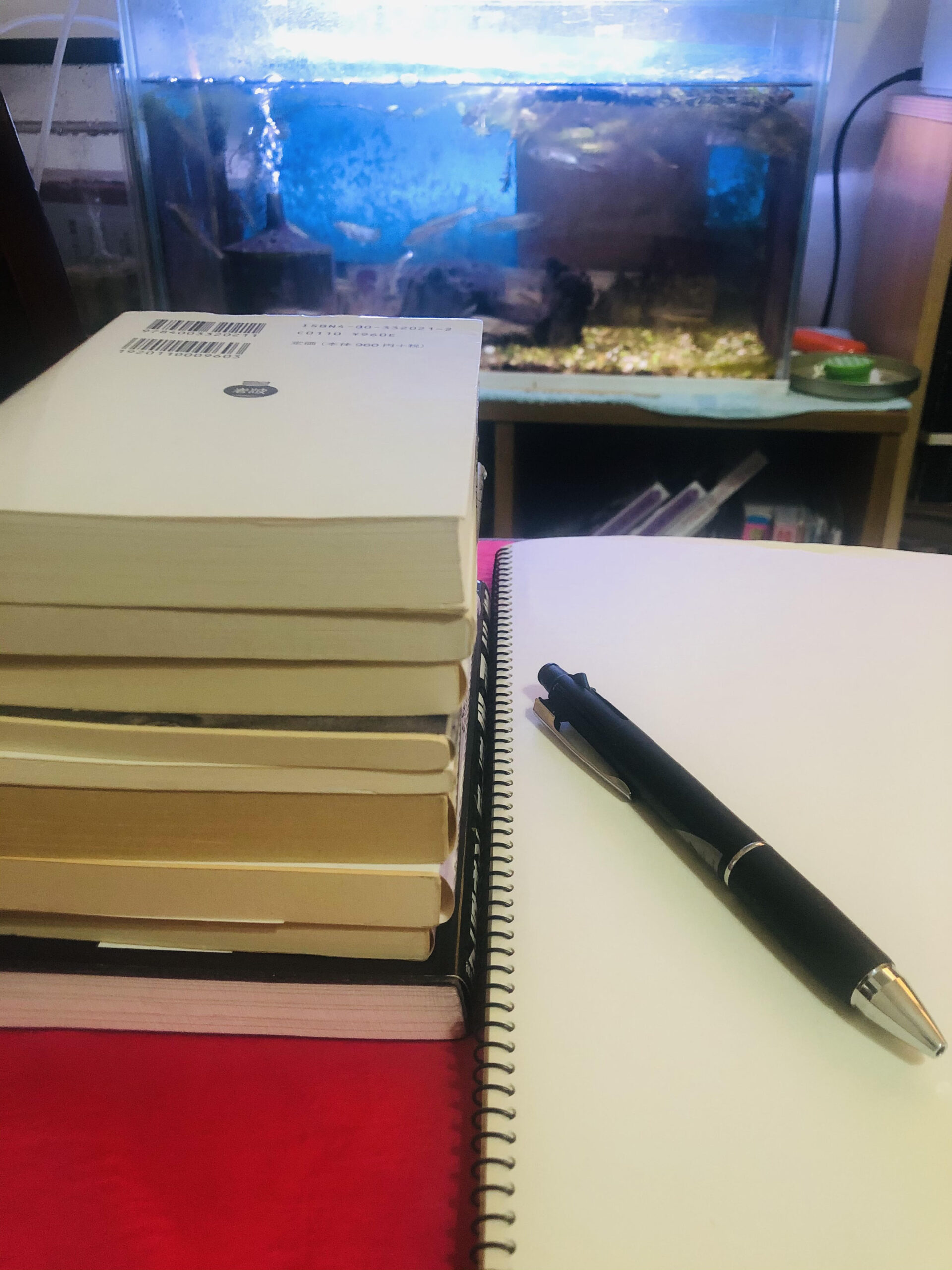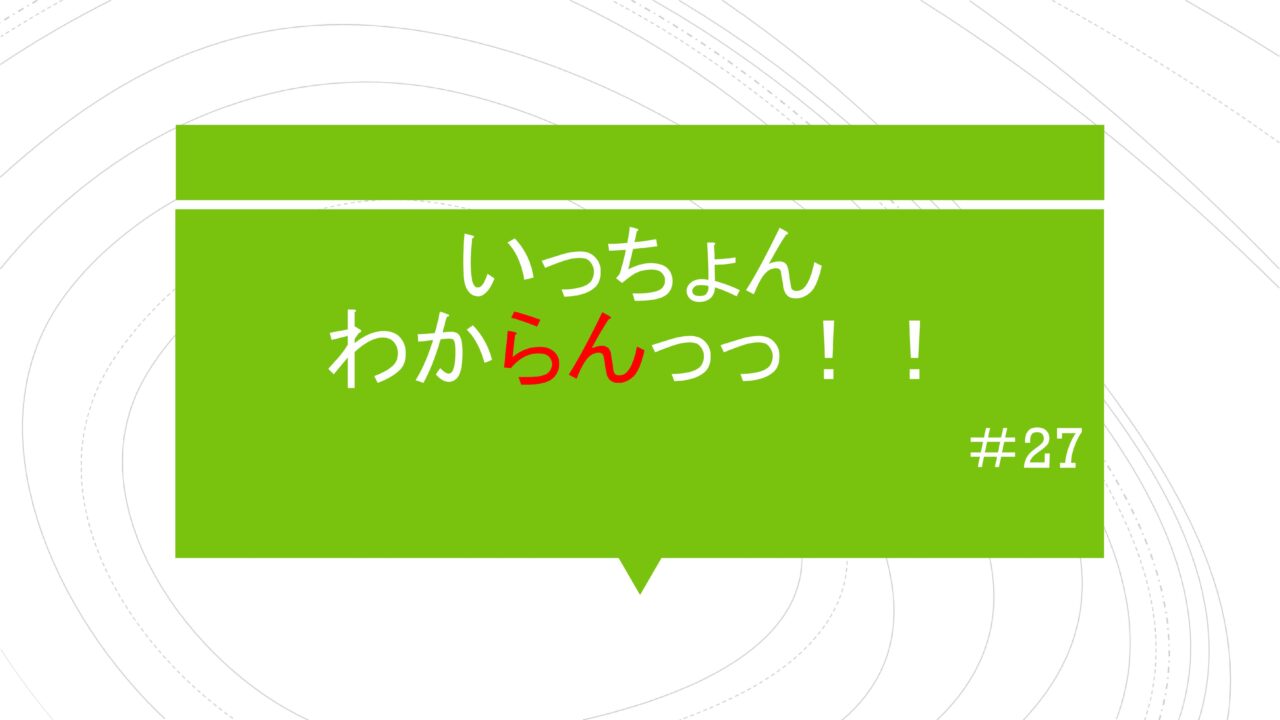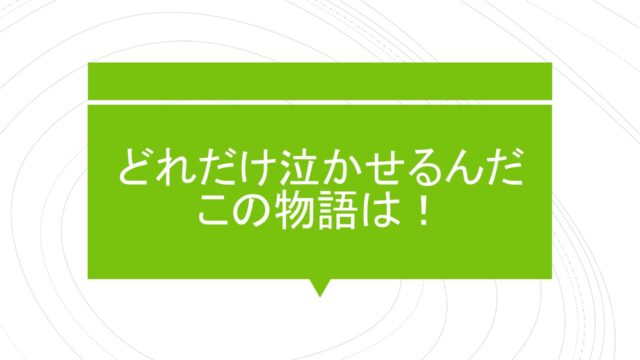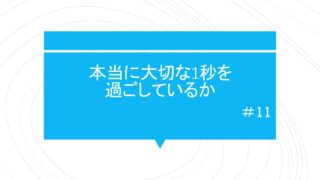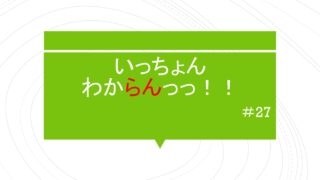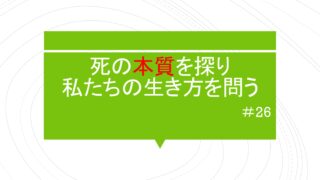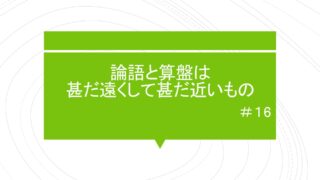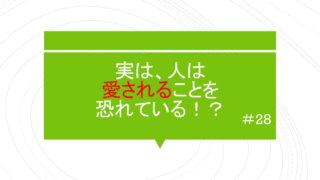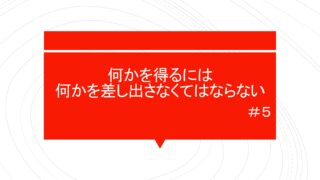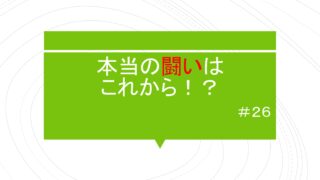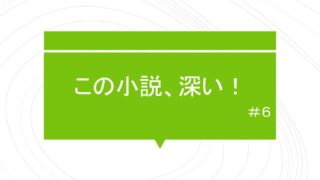文部科学省の調査によると、中高生の英語力が上がってそうです。同調査では、中学3年生で英検3級程度、高校3年生で英検準2級程度の英語力がある生徒の割合を調べました。結果を見てみると、40%代が軒並みで50%を超える地域もある。PISAの結果等を引き合いに出した学力の低下が話題に上がるが、今回のような結果は純粋に現中高生の努力の賜物だと認めるべでしょう。
うらみわびの【この本がおもしろい!】第27回 今回は「青ブタ」シリーズ第3弾!
『青春ブタ野郎はロジカルウィッチの夢を見ない』(2015)を読む
 |
|
青春ブタ野郎はロジカルウィッチの夢を見ない (電撃文庫) [ 鴨志田 一 ] 価格:671円 |
![]()
| 勝手に評価表 | |
|---|---|
| 内容 | ★★★★☆ |
| 難しさ | ★★☆☆☆ |
| 価格 | ★☆☆☆☆ |
ある日突然、体に無数の傷ができたり、他者から存在が認識されなくなったり、同じ日を繰り返したり…、人々はそんな不可解な出来事を「思春期症候群」と呼び、都市伝説化していた。その存在を本気で信じている人は少ない。しかし、それは確実に存在していた。それを知る男子高校生、梓川咲太。これまでいくつもの思春期症候群を目撃してきた咲太であったが、夏休みの終わりを目前に新たな思春期症候群を目にすることとなる。現代を取り巻く人間心理を鮮やかに描く青春小説第3巻。
ここに注目!
作者いわく、毎回メインとなるヒロインが異なる本シリーズであるが、本作では双葉理央にスポットが当たる。地味系理系女子の彼女だが、彼女は表には出さないある思いがあった。その思いが本人も想像もつかない展開へと皆を導いていく。何が彼女をそこまで駆り立てるのか?その正体を明確に突き止めるのは難しいかもしれない。それでもこの小説は可能性の一片を明確な表現で私たちに示してくれている。これは現代青春小説というジャンルがなせる業なのかもしれない。
さわやかな表現光る!
夏の湘南の青春。これほどさわやかな題材はないだろう。本作は深遠なテーマを抱きながら、それを感じさせないさわやかさで描き切った大作だ。特に後半の一連の出来事は著者の鴨志田先生も筆が走ったのではないだろうか。勢いのある表現が多かった。今作の出来事は台風のようにやってきて、去っていった。終わってみれば晴天であるが、そこに至るまでには様々な葛藤があったことがうかがえる。幼児期と成人期を比べれば、精神の闇の深さは一目瞭然だ。どこで差がうまれたのだろう。思春期という多感な時期、という可能性は十分にある。しかし、それは思春期特有のことなのだろうか。成人はメンタルが成熟していて強いから? では、思春期の学生たちはメンタルが未熟なのだろうか。そんな疑問が頭に浮かんだ。
答えは否ではないか。咲太の行動を見ればそう思わずにはいられない。彼はこれまで多くの辛い体験を目の当たりにしてきた。それらが彼の凡人離れした言動に如実に表れている。それらには舌を巻くばかりだ。
本作のテーマは2つあるように思う。それは人格の多源性と、感謝の言葉を言うことの難しさである。
複数いる「自分」
最大の難関”自己嫌悪”
「こんなの自分じゃない」、「こんな自分は嫌いだ」。そう思ったことがある人は多いのではないだろうか。自分が嫌いでしょうがない。この悩みを和解するのは容易なことではない。
(自己嫌悪は「解決するべき問題」ではなく、自分のなかでうまく辻褄をあわせることだ、と私は考えているので、本題を「問題」ではなく、「課題」、それに対して「解決」ではなく、「和解」という言葉を用いる)
悩みの根は深く、下手に手を出すと取り返しのつかないことになるからだ。したがって、このような自己嫌悪の課題はメンタルの分野において最難関の部類に入る、と私は思っている。
この課題に対しては私もいろいろと考えを巡らしてきてはいるが、いまだに明らかな糸口はみえてこない。ただ、いえることは一つある。それは、答えはひとつではない、ということ。具体的には、課題の根はひとそれぞれ異なり、根本をしっかり把握してからでないと、和解へのアプローチをとることはできない。
本人だけができる「和解」
本作は2つ目のことを私に教えてくれている。それは、和解は最終的に本人にしか行えない、ということである。当たり前のようではあるが、私はこれを見落としていた。他者の視点から救いの手を差し伸べることは究極的には不可能だということだ。伴走はできるが、最期の数キロ~ゴールは自分一人で行かなければならない、ということだ。「自分の力だけで他人を絶望から引っ張り上げるのは不可能だ。それができると思えるほど傲慢にはなれない。」と咲太は言った。彼は理央を救うために体を張って付き添ったが、最終的には彼女の判断にすべてをゆだねた。自殺をほのめかす彼女を止めなかったのだ。正確には止める言葉がなかったのかもしれない。しかし、これが正しいのではないか。複数の自己の存在は自然だと解するが、自己の分裂は自分自身でも錯乱した状態にあり、「やってはいけない」という一般論はまったく効果をあらわさない。それは本人だってよく分かっているからだ。これはいわゆる「依存症」とよばれるものと闘っている人たちの日常をみると分かりやすい。
最終的には自分で複数の自己同士を和解させるしかない。その手助けを他者が行うのであれば、まずは相手の悩みに耳を傾け、時には居場所を提供し、時には一人の時間を確保するのがよいだろう。そのさじ加減はサポーターの観察力にゆだねられている。大切なのはサポーターが自分のなかで判断を下さず、本人の話の中から和解の糸口をさぐることである。これは現代カウンセリングの祖、カール・ロジャーズの手法と一致するだろう。和解の鍵は本人のなかにあるのだ。
複数の自己があるのが自然である。それは私たちがプライベートから仕事まで、様々な環境に身を置くことから分かる。それぞれの場面において私たちは半ば無意識のうちに自己のあらゆる要素を調節して適応している。これはかなり複雑化しており、プライベートひとつとっても友人とダベる自分から親友と深い話をする自分、パートナーに対してありのままをさらけ出す自分、誰にも見せない自分、など様々な自分がいることに気づくだろう。それらは間違いなく全て「自分」なのである。
しかし、世の中には罠が潜んでいる。それが人間としての「あるべき姿」というステレオタイプだ。私たちの中には、今よりさらに高みを目指したい、という上昇志向がある。高みを目指すことはTry & Errorである。つまり、挑戦と自己の修正がセットになっている。自己の修正に関してはこれを難なくこなせる人もいれば、苦手な人もいる。これまでの自分をいったんは否定することになるからだ。この一連の動作の繰り返し、もしくは社会からの強要が自己嫌悪を助長させている、と考える。
SNSがはらむ”矛盾”
近年のSNSの発達も自己嫌悪に拍車をかけている。それは単に他者から誹謗・中傷をうける機会が増えただけにとどまらない。ネットは構造上、すべての人が情報にアクセスできるように作られている。したがって、プライベートの自己を仕事上の関係者に見られる、という可能性が高まったのだ。ネット上では複数の自己の存在が自然であるのにも関わらず、社会的な目を気にしなければならない、という矛盾が起きているのだ。これを回避するためには発言内容によって複数のアカウントや発言ツールを使い分けることが求められるようになってきた。これで表向きは解決するようにみえるが、そうではない。心のどこかで、このようなことをしなければならない自分に嫌悪感を抱くからだ。社会的に批判される自分の一面は本当に悪い一面なのか? 面と向かって話せば普通に話せるのに、ネットの世界では自分の一面を隠さないといけないことに対して疑問が生じる。それでも社会のなかで適応していかなければならない。でないと抹殺されてしまうからだ。いつからか、私たちは自分を殺して生きている。
これを心理学の側面からみると、スイスの精神科医、カール・グスタフ・ユングの「ぺルソナ」と「シャドウ」という考えがある。
- ペルソナ…他者にみせる自分
- シャドウ…他者に隠している自分
先のネットの例では、ぺルソナが表向きのアカウントであり、シャドウが裏アカウントである、といえる。この概念にとって大切なことはシャドウを克服の対象とするのではなく、和解の対象であるということだ、と私は考えている。社会からすれば悪とみなされかねない自分、そんな自分は嫌にもなるが、無意識のうちにそんな影の自分の存在によって私たちは光の自分を保っているのだ。影の自分も受け入れよう。
ここから、個人の外の世界からのアプローチ、についても見えてくる。それは、「あるべき像」で個人を縛り付けないことだ。人の影を暴くこと、それを見て消費することは快感であるが、そんな私たち一人ひとりにも影の部分があるのだ。時にはぺルソナによって疲弊し、シャドウが暴走することもある。そんな可能性を誰もが内在している。そのことを我々が少しでも認識しておくことが自己嫌悪に苦しむ人々を減らす助けになると考える。