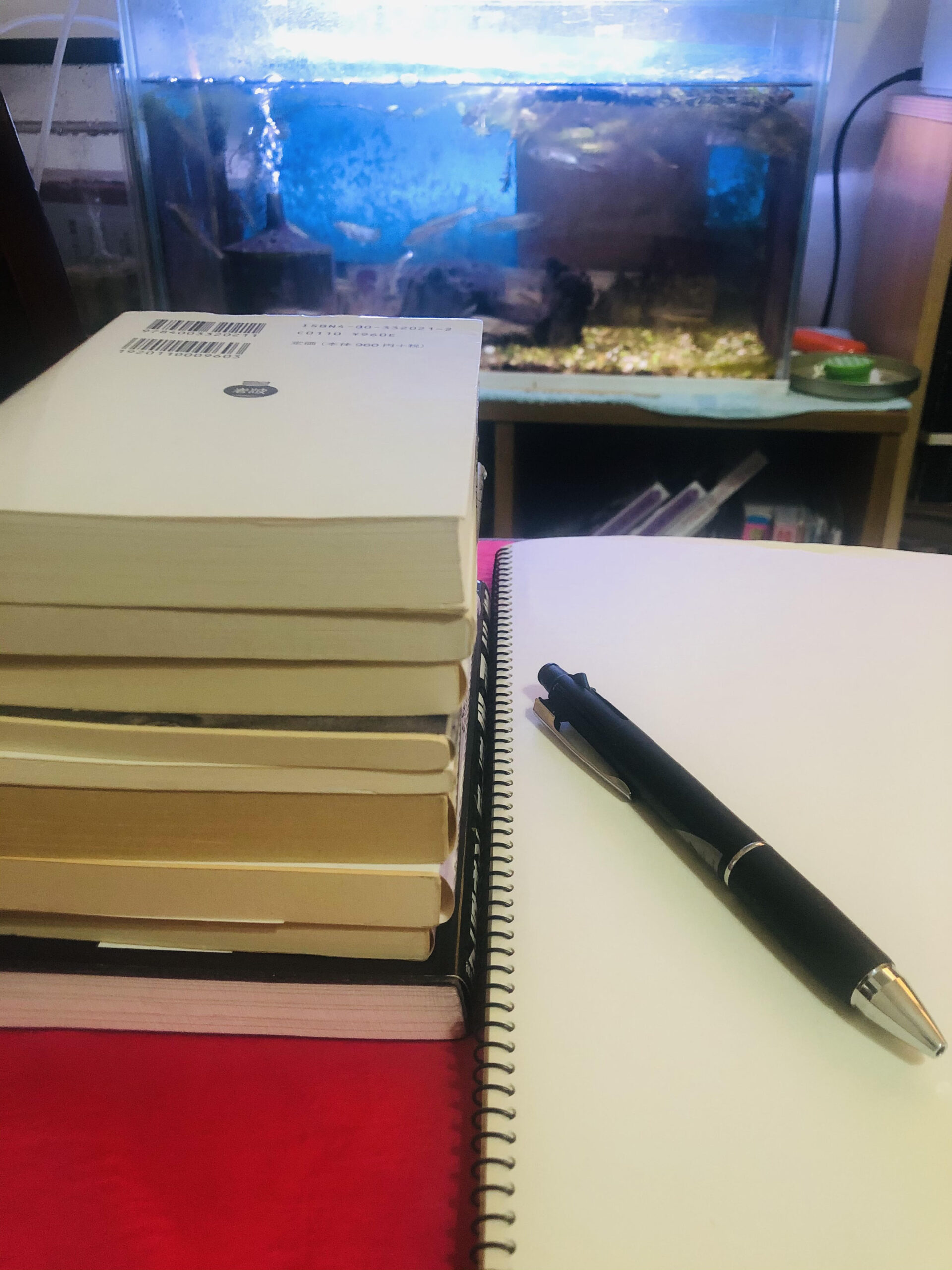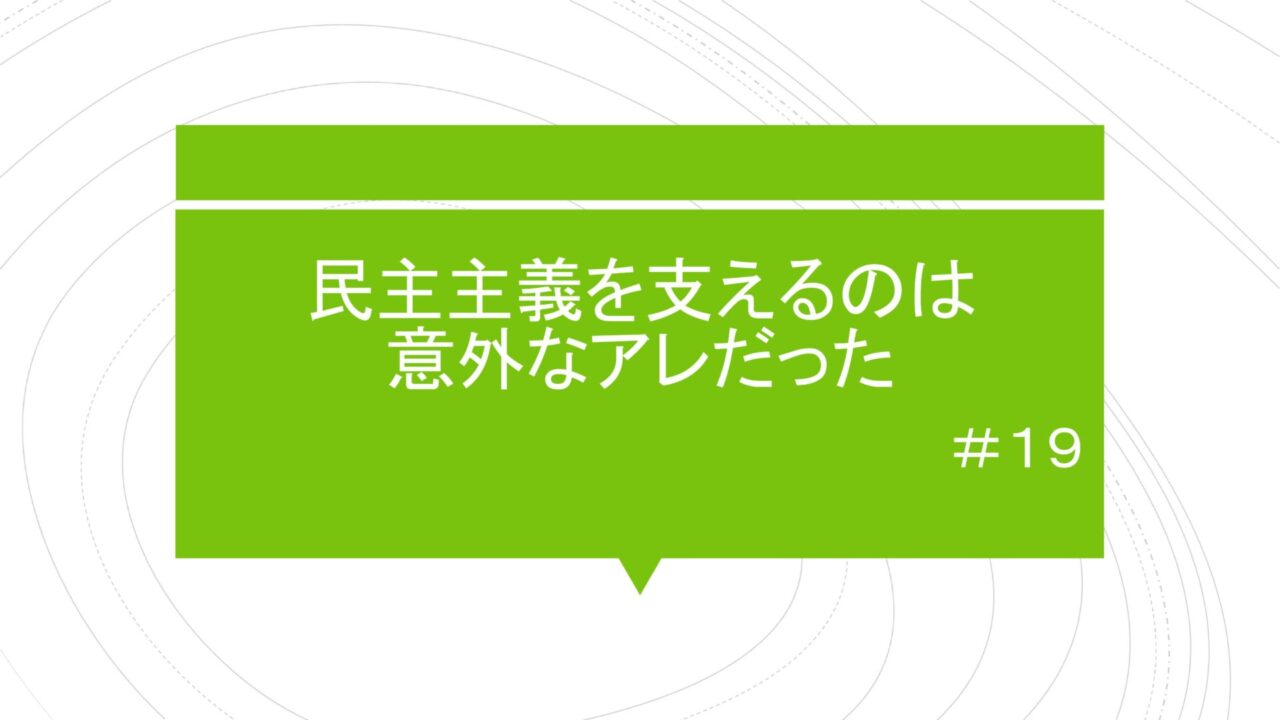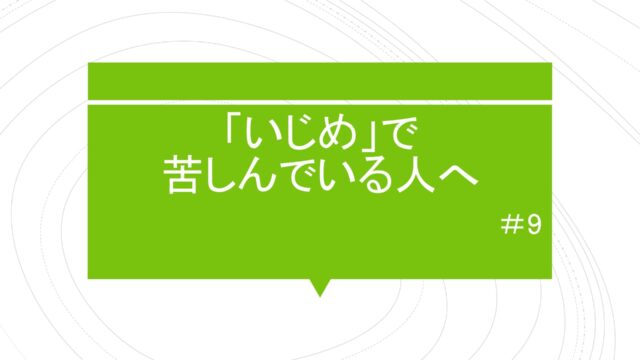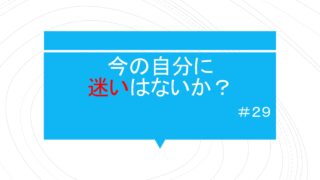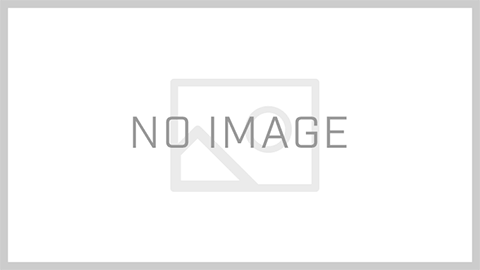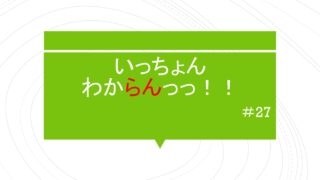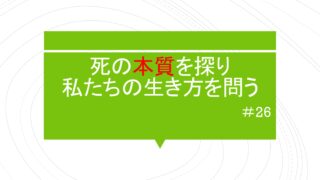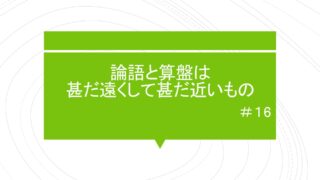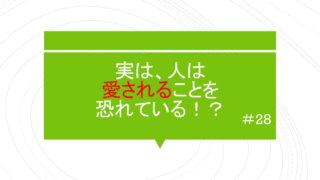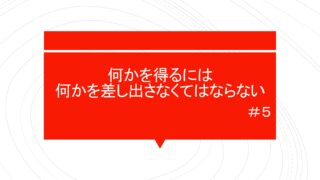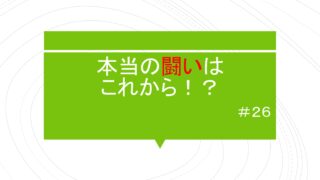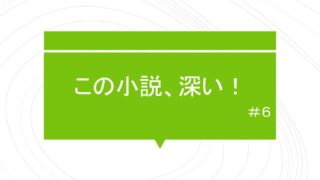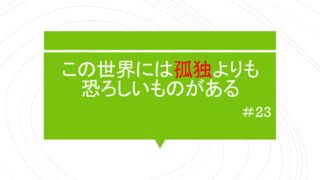うらみわびの【この本がおもしろい!】第19回
アメリカ軍が順次撤退を表明したアフガニスタン。
アメリカ軍の撤退の準備が進む最中にイスラム教系勢力タリバンが政権を奪取した。
イスラム教の主義を重んじるタリバンは女性の権利については「イスラム教の範囲内」で尊重するという姿勢を示し、社会の形態については「民主主義は適さない」と述べる。
過去の政権崩壊から約20年。アメリカの支援による民主主義国家として存在してきたアフガニスタン。その行く先に注目が集まっている。
今回の事例は私たちが目指すべき社会の在り方、つまり日本でいえば民主主義がいかにあるべきか、ということについて、改めて問いを発しているように感じる。
果たして民主主義は適した社会の在り方なのだろうか。少なくとも最善の在り方である、といえるだろうか。
そこに不備はないか。弱点はないか。問題はないか。私たちには不断の考察が求められていよう。
そこで今より1世紀前、”民主主義”に関して非常に深い考察をされた書籍を紹介する。
ハンス・ケルゼン著 長尾龍一・植田俊太郎 訳
岩波書店(2015)
『民主主義の本質と価値』
 |
|
民主主義の本質と価値 他一篇 (岩波文庫) [ ハンス・ケルゼン ]
|
![]()
| 勝手に評価表 | |
|---|---|
| ストーリー | ★★★★ |
| アクション | ★ |
| 感動 | ★ |
国家を運営するには……
本書が執筆されたのは戦の匂いがきつい1900年代前半。ちょうどドイツでは民主主義の革新的な憲法として注目されていたワイマール憲法の限界が示唆されていたとき。ナチスドイツの台頭が見られようとしている時期である。
この時期ほど”民主主義”というものが危機に瀕していた時期はないだろう。国家という共同体を組織し運営するにはどうするのが最善か。マルクス主義のような社会主義思想が台頭しているなど、”社会の在り方”が盛んに問われている時代であった。
そんな時代においても「民主主義こそが事実上の権力状況に適した唯一の表現形態である」と筆者は主張する。本書は法学者である筆者ハンス・ケルゼンによる、民主主義の深い洞察が感じられる本である。
民主主義とは何か、多数決原理の課題とは、民主主義は現代の社会に耐えうるものか。執筆から100年余り経た現代においても十分読みごたえがある。”民主主義”の議論の一端を担う本書は一読に値するだろう。
「集団の総意」を突き詰める
”民主主義”というと多数決を想像する。複数人で物事を決めるとき、この多数決こそ「民主主義的」な決め方と考えられる。
この多数決も完全なる決め方ではないように思われる。というのも多数決によって決められた案は「多数派の」意見であり「集団の総意」とはいえない、といえるからだ。
人間というのは実に多様な考え方をもつ生き物である。あまりよい例ではないが、昨今のコロナウイルスにおける言説、例えば「ワクチンを打ったらマスクをしなくても外出してよい」という意見を持つ人が世界を見渡すと一定数いる。この現状に納得する人もいれば大きな嫌悪感をもつ人もいる。両者が道端で出会えば、ケンカではすまないかもしれない。これはほんの1例である。様々な事象を考慮すれば、本当に人間は多様な生き物である。
そんな多様な思想をもつ人間が集団を形成する。そこで物事を”決める”という作業はどれほど難しいことか。ましてや「集団の総意」なるものは存在しえるのだろうか。
かつてギリシアでは集団の構成員全員が議論に参加し投票する、という直接民主制がとられていた。だが、これは人数が少ない集団でおいてのみ可能な方法。現代の国家のような膨大な集団には適さない。そこで出てきたのが選挙によって国民の代表者を選び、その代表者を通じて国家を運営していく、という間接民主制である。
間接民主制は代表者を通じて国家規模の物事(例えば法律)を決めていくので、非常にコンパクトで利口な方法である、といえる。
しかしながら、選挙によって選ばれた代表者が、選挙でその人を選んだ人(選挙区の有権者)の民意を全て反映した行動をする、とは到底考えられない。彼・彼女も一人の人間であり、なにより選挙区における限られた有権者でさえ、統一した「集団の総意」というものはつくることができない、といえるから。ここでも集団における総意が不可能である、ということの根拠となる。
そんなこんなで、文字通りの「集団の総意」とういのは到底不可能な夢である、としかいいようがない。
ここまで長々と書いてきたが、端的に申し上げれば、多数決に代表される民主主義ではその過程で必ず”死票”がでる、ということである。いいかえれば、「私の意見が反映されていないよ」と言う人が出てくるのが必然なのである。
”死票”は民主主義の産物、というのは適切な表現ではないだろう。というのも、そもそも多数決原理というのはこの死票を極力少なくする方法だからである。
投票行動を通して多数派の意見を吸い上げる。そうすることで、言い換えれば、少しでも多くの人が納得のいくかたちでの決議を可能にしているのだ。
集団を支える「妥協」
では、少数者の意見はないがしろにされているのか。「そうではない」というのが筆者のハンス氏。そこには”妥協”という考え方がある。
私自身、「おもしろいな」と思うのは選挙における”比例代表選”である。これも国家ごとに微妙に制度は異なるが、その本質はできるだけ多くの政党に議席を分配する、というところにある。
要は野党の存在が政治に影響を与える、という可能性がある、ということである。ここが大切。
与党といえども、すべてを自らのやりたいように決めて実行していては独裁や専制君主となんら変わりがない。
時には与党の暴走を止める、または意見を深化させていく存在が必ず必要だ。
それが野党である。議会で少数派の野党が与党を批判する、または対案を示す。与党がそこに反論する、歩み寄りを見せる、というのが健全な政治の進行だろう。
ここでの与党の”歩み寄り”こそがケルゼンの言う「妥協」とうことになるだろう。
この妥協というのは一見、私たちにとって盲点であり、かつ重要なことである、と考える。民主主義的方法によって選ばれた代表者は、ただ多数派のひとりよがりな意見に支配されることなく、少数派の意見を取り入れた、両者の中間地点に近い場所に着地するように議論が行われる、ということである。
これは政治的パフォーマンスでもなんでもない。そのようになるべきであるし、そうなるようにうまく仕組みが構築されているのである。例えば日本における憲法改正の発議に必要な議席数は「各議員の三分の二以上の賛成(日本国憲法第96条)」とあるように、かなり大きなハードルを設けている。これは単なる多数派というだけでは超えることの難しいハードルだ。このように大きな影響力のある決議に関しては大きなハードルを設ける。なんとか政策を可決させたい与党は、ある分野では妥協し、その見返りにある分野では野党に妥協してもらう。そのようなことが自然とおこる。そうすることで多数派と少数派の意見のすり合わせを促しているのである。
少数者を守れ!
合わせて大切になるのが少数派を守る、ということである。多数派は多数派である限り安泰である。多数派とは換言すれば「仲間が多い」ということだからである。
一方、少数派はその面で軽んじられることが多い。アフガニスタンで女性の身の安全が心配されているのは、タリバン勢力(多数派)が女性の社会への参画において否定的な見方をしている、と感じているからだ。
ケルビンいわく、平等権や自由権といった諸所の権利は、特に少数者にむけられたものである、という。”平等”や”自由”といった権利概念は一定の制限をうけながらも絶対的である、という面で多数決原理より上位に位置する概念である、ということがわかる。そんな権利を憲法でしっかりと保証することで少数者の立場も守られているのである。
民主主義とは、できる限り多くの人々の意見を反映させるシステムにほかならない。そこには多数派と少数派の意見双方を取り入れるようにする仕組みや少数派を守る仕組みが盛り込まれている。
多数決原理や自然権といったものは、こうした民主主義の理想が具現化したものである。
 |
|
民主主義の本質と価値 他一篇 (岩波文庫) [ ハンス・ケルゼン ] 価格:726円 |
![]()