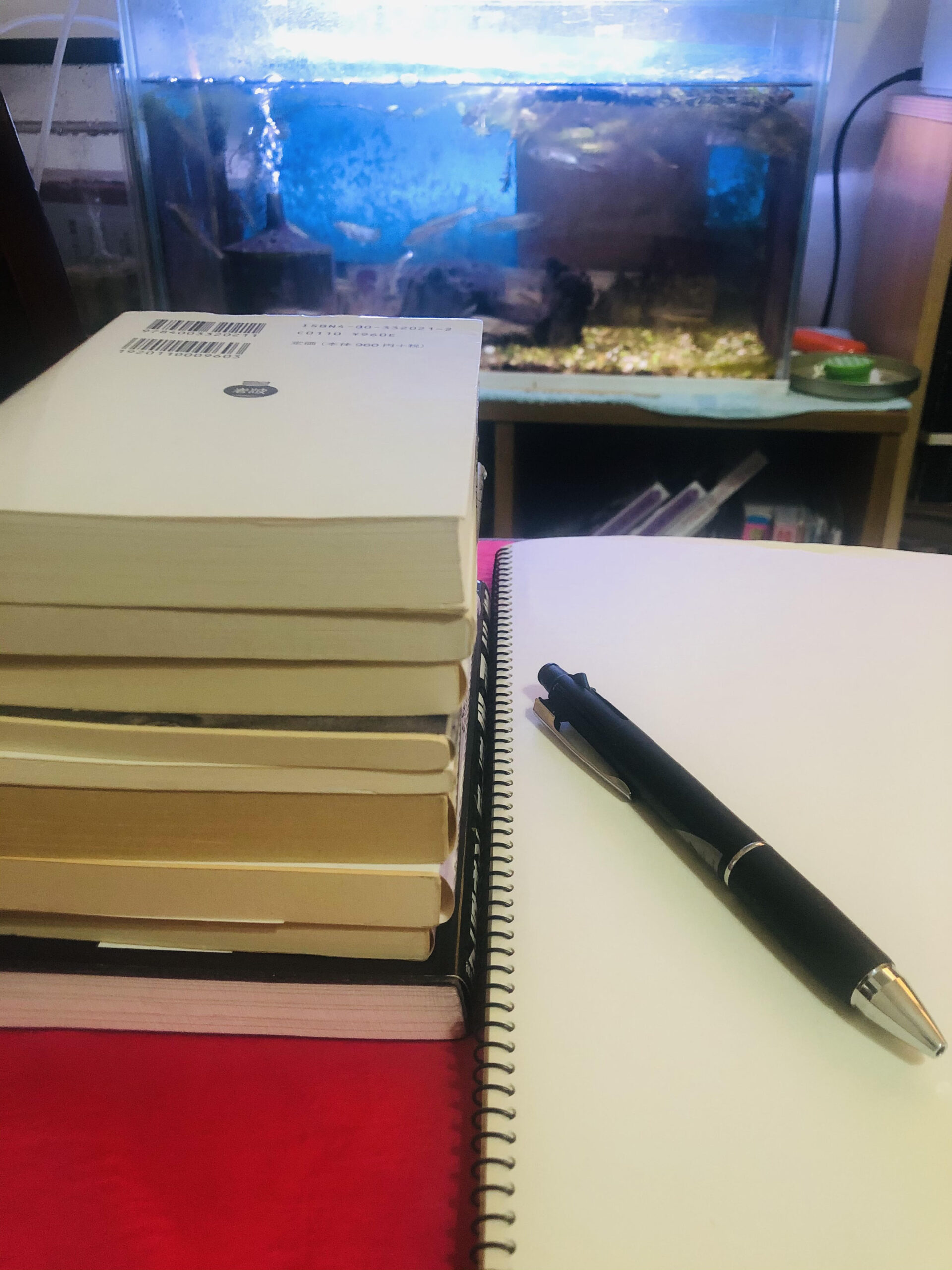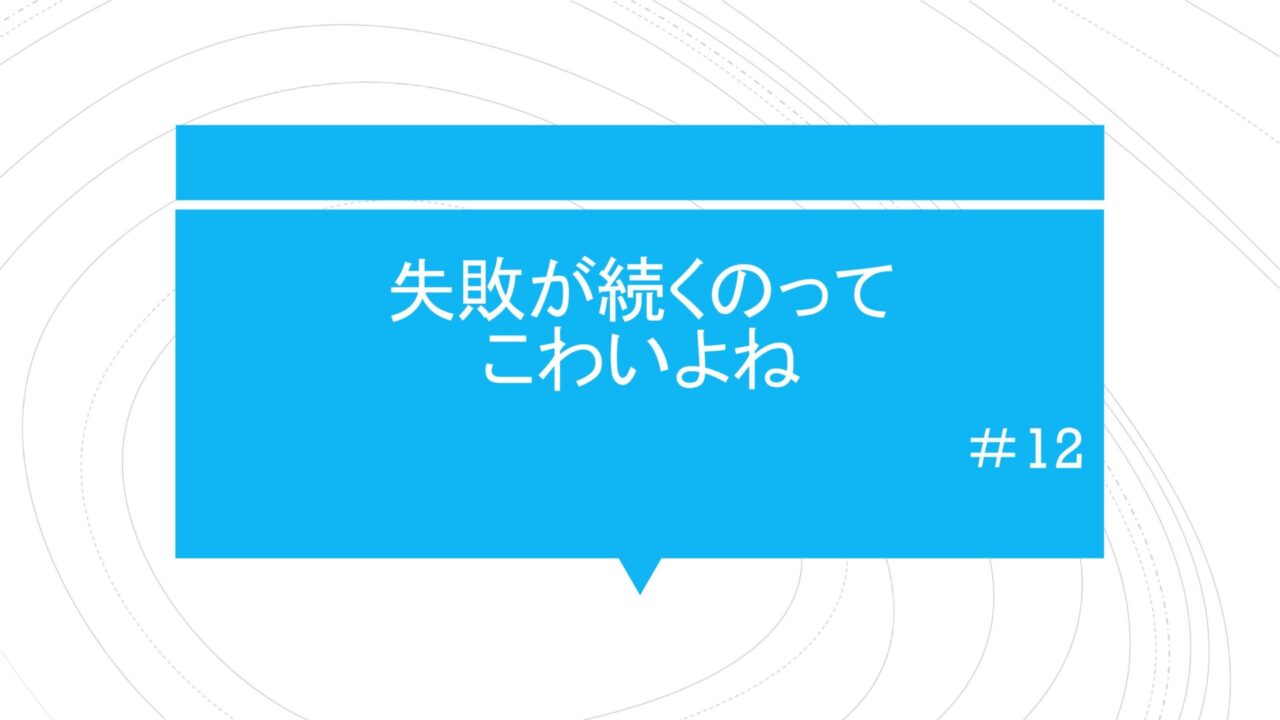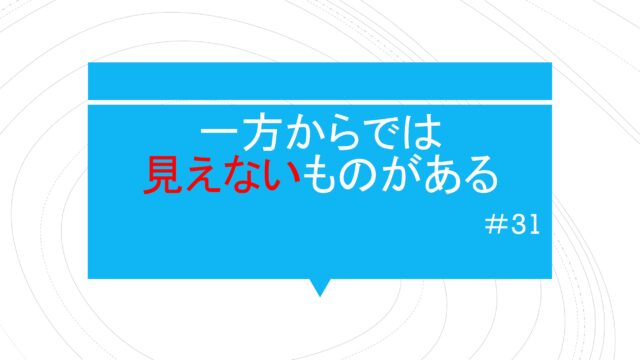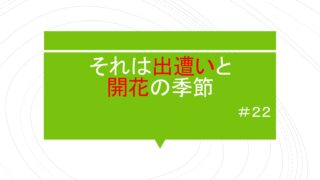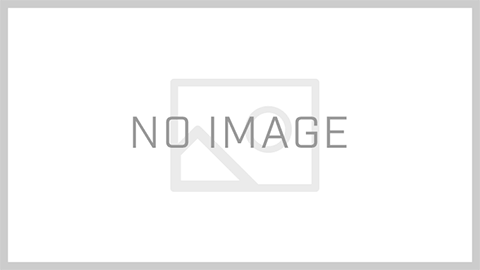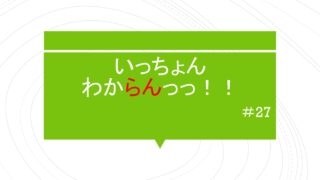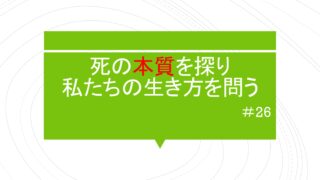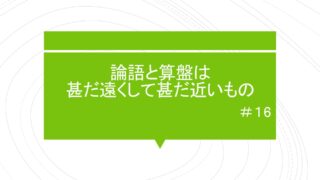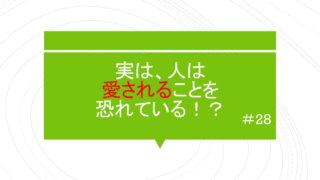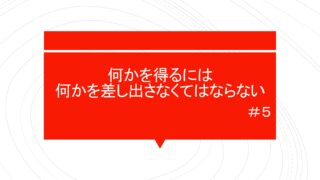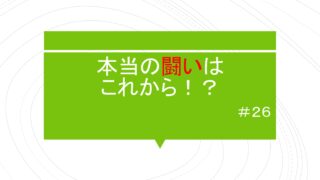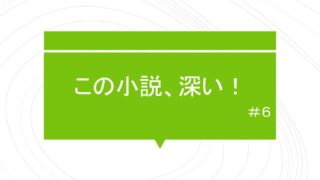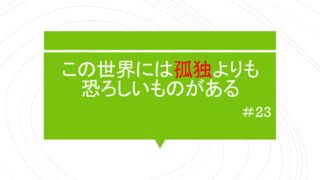うらみわびの【きょう考えたこと】第12回
「生きていれば失敗することもある」。こう割り切ることが求められていることは重々承知している。なぜなら人生とは失敗の連続だからである。
いやなことに失敗は呼んでいなくても、あちらからやってくる。
先日、職場の同僚に欠勤者がでたため、私が5連勤することになった。5連勤もすると、大体1つか2つは問題が起こるものである。用心していても問題は起こるものなので、これは考えても仕方がない。
しかし、分かっていても失敗が怖いのが正直なところ。「失敗のない人生」なんてものがあれば、それを選ぶのではないだろうか。
「失敗のない人生」。それに対する憧れは、私たちが普段、どれだけ”失敗”を恐れ、ストレスを感じているか、を明らかにする。
では、失敗のない人生が人々を幸せにする、と結論付けてよろしいだろうか。
いや、待てよ。私は以前から言ってきたではないか。「経験こそが大切である」と。
「経験から学ぶ」というが、ここでの”経験”とは”失敗”の経験に他ならない。私たちは失敗することで学ぶのである。
私たちには「好きなものを食べる」という自由を謳歌している。野菜から肉からなんでも食べる。
この食の自由も実は先人の失敗の賜物である。例えばフグを食べることができるのはフグの毒に当たった人がいるからである。キノコを食べることができるのは、その種が安全である、と実際に確かめた人がいるからである。(ちなみに地球上のキノコの約8割がいまだに食用か証明されていない、という)
考えれば考えるほど、私たちの生活は人々の”失敗”であふれている。実は失敗こそが私たちの暮らしを豊かにしているのだ。
では、なぜ私たちは”失敗”を恐れているのだろうか。それは失敗に対する他者からの叱責を恐れたり、失敗によって自らの財を失うことを恐れているから、だと考えられる。前者は他者と、後者は自らに関係している。
残念ながら自分以外の人々をコントロールすることは不可能である。したがって他者からの叱責を直接減らすことは難しい。
反対に自らが作り出す失敗への恐怖はある程度緩和が可能だ。自分が変化すればよいのだから。
残念ながら”失敗”そのものを完全になくすことはできない。必要なのは失敗を”受け流す姿勢”である。
哲学者のアランは”幸せ”への近道として行動、すなわち「実践」を重要視した。今回のことに換言すれば、失敗をなくすのではなく、生きていきながら失敗をいなしていく、ということである。
わたしは言いたい。現在のことを考えよ、と。刻一刻とつづいている自分の生活のことを考えよ、と。時は刻々と移っていく。だから、きみは現に生きているのだから、きみが現に生きているように生きていくことは可能である。しかし、君は未来がこわいのだなどと言う。君は自分の知らないことを話しているのだ。
できごとというものは、けっして私たちの期待していたとおりのものではない。それにきみの現在の苦痛に関して言えば、まさにそれがたいへん激しいものであるだけに減退することを確信することができる。
すべてはは変わり、すべては過ぎ去る。この格言は、しばしばわたくしたちをかなしませるものだ。しかし、ほんのわずかでもときには、わたくしたちを慰めることもあるのだ。
アラン『幸福論』
つまるところ、失敗が私たちを成長させ、失敗が私たちを豊かにするならば、私たちは失敗を受け容れなければならない。
でも、私たちは多くの失敗を受け容れることができるほど強くはない。
ここでは工夫が必要そうだ。失敗をこまめに取り入れていくのだ。自らが1日のうちに消化できる範囲の失敗にとどめるように用心し、成長していくのが良いだろう。
言い換えれば、必要以上に後悔し、落ち込まないことである。人間には1日のうちに吸収することの出来る学びの限度というものがある。これは私たちが際限なく食事をすることができないのと同じである。
失敗を少しづつ取り入れていく。もしもこの世の私たちがコントロールすることの出来ない種々の事象を神様なるものがコントロールしているとするならば、5日のうちに1つか2つの失敗と挑戦を設けてくれたのは幸いなのかもしれない。
不安を直視する
(追記:2021年9月1日)
一方で、失敗の不安から逃げることなく、それを直視することが肝要である、とするのが哲学者のラッセル。
恐怖が心に忍び込んでくると、その都度、別のことを考えようとする。娯楽とか仕事とかで考えをまぎらわそうとする。
ところが、あらゆる種類の恐怖は、直視しないことでますます募ってくる。考えをよそへ向けようと努力すれば、目をそむけようとしている幽霊が一段とこわいものに見えてくる。
あらゆる種類の恐怖に対処する正しい道は、理性的に、平静に、しかし大いに思念を集中して、その恐怖がすっかりなじみのものになるまで考え抜くことだ。
ラッセル『幸福論』
確かに、あえて何か楽しいことを考えたり、一度寝てみる、というのは不安に対処する常套手段としてある。これはこれでかなり効果がある、と実感している。
一方で、問題は本質的には解決していない。以上の行為は問題を後回しにしたに過ぎない、ともいえる。
しかし、そうとも限らないだろう。ここには私たち、人間の存在がある。人間とは目だけでなく、心を通して物事を見ている。
私はうつ症状をもっている。私は登山やゲーム、読書が好きだ。興味深いことに、うつ症状が前面に出ている時は、これらの趣味がまったくもっておもしろくない。これは物事としての対象である趣味自体がおもしろくないのではない。趣味を行う私自身に問題があるのである。そして、その問題は私の精神面にある。
不思議なことに、うつ症状とは永続的には続かない。長さの長短はあれど、いつかは自然な心の状態に戻る。その近道として、睡眠やなにか機械的な作業に打ち込む、散歩などの秘策がある。
つまり、私たちは人間である以上、心の目を通して物事を捉えている。なにか「辛い」、「こわい」出来事がある、とすれば、それは私たちの心が「辛い」、「こわい」といっているのである。
そして前述した通り、心とは流動的である。ネガティブな時もあれば、ポジティブな時もある。このような変化は個人差はあれど、人間ならいたって自然なことである。
注意したいのは、何か漠然とした不安や恐怖があるとき、それは自分の心が「現在」悪い状態にあるのではないか、という疑いを持つこと。どうか時間をかけて自らの心と、不安と向き合ってほしい。
ラッセルが物事を直視せよ、と述べるのはもっともである。一方で、それは自らの心の状態が良いときに限る、と申し上げておく。
不安がある。ならば、まずは心の自己診断。結果がアウトなら、まずは休む。これが重要。問題を直視するのはあとでも遅くはない。
したがって、アランとラッセルの両論は矛盾せず、むしろ一貫したものである、と考える。
今日も皆さんが幸せでありますように
 |
|
価格:715円 |
![]()
 |
|
幸福論(ラッセル) (岩波文庫 青649-3) [ ラッセル,B.(バートランド) ] 価格:924円 |
![]()
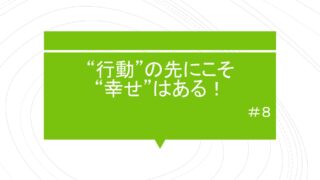
#RPG #SF #いじめ #うつ病 #アニメ #エッセイ #オクトパストラベラー #ゲーム #スクエニ #ニーチェ #ファイナルファンタジー #ファイナルファンタジー4 #ファイナルファンタジー4 #フィクション #メンタルヘルス #リモート旅行 #京都アニメーション #人間関係 #人間関係の悩み #働き方 #単行本 #哲学 #夏 #孔子 #学校 #学習 #家庭 #小説 #幸せ #恋愛 #憲法 #憲法改正 #戦争 #政治 #教育 #文庫 #木村草太 #本が好き #正しさ #社会 #組織 #自分磨き #自殺 #適応障害 #集団的自衛権