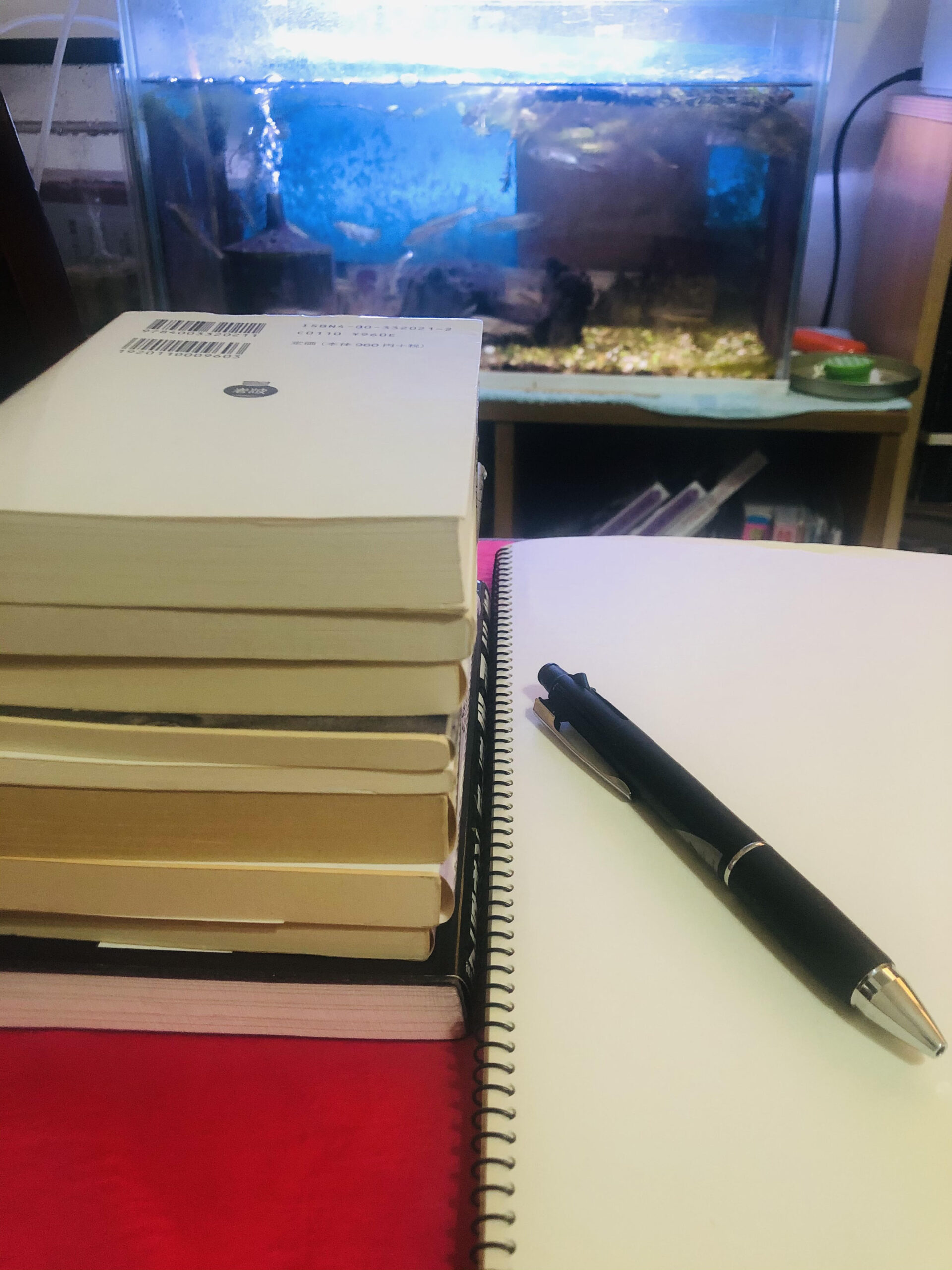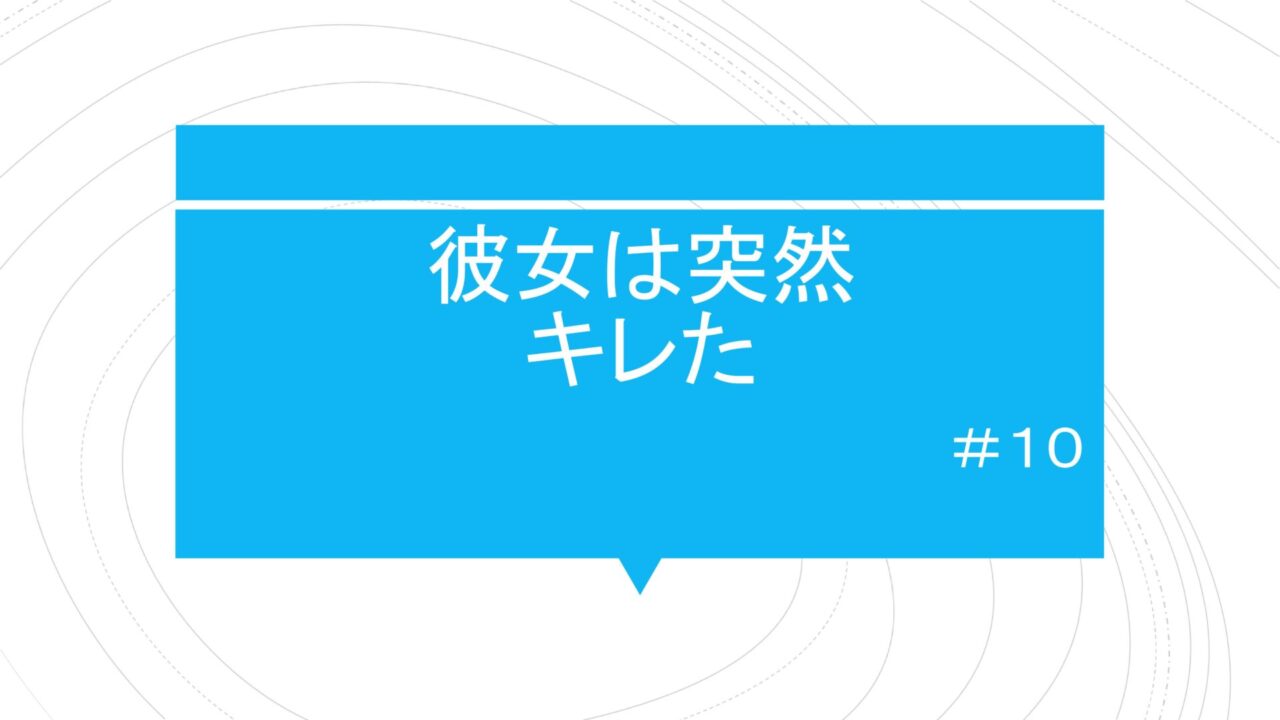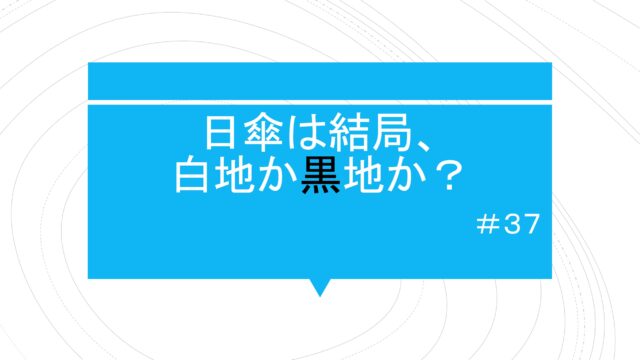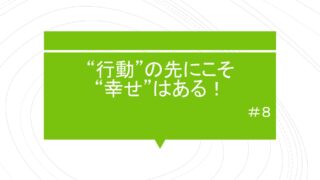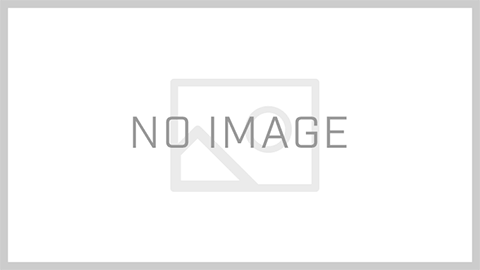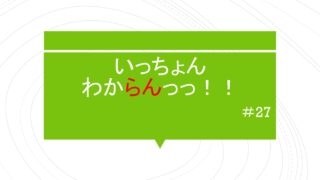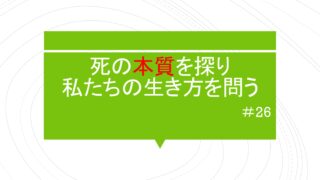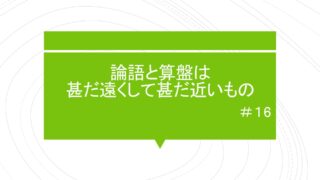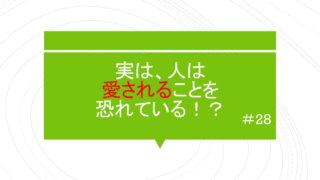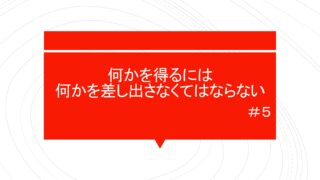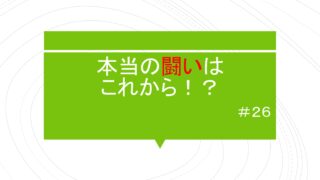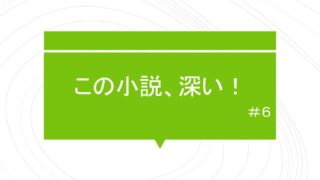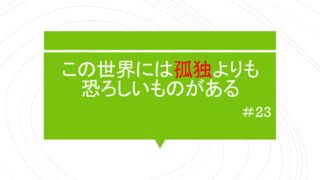うらみわびの【きょう考えたこと】第10回
我が家では時折、小学生の従妹たち2人が夕食を食べにやってくる。
今夜はたこ焼きをつくって食べることになった。従妹いわく、このたこ焼きパーティ(タコパ―)は結構楽しいイベントである。
しかしながら、従妹たちにとっても私にとっても、この楽しい時間に水を差す出来事が起こってしまった。
たこ焼きを焼くのは叔母と決まっている。従妹たちは焼けたたこ焼きをひっくり返す係だ。
しかし、たこ焼きが焼けても従妹たちはなかなかひっくり返そうとしない。叔母のスマホでユーチューブを見ているのだ。
「ちょっと、タコひっくり返してよ」叔母がぼそっと言う。それでも従妹たちはユーチューブを見続ける。
それから2分ほどが過ぎただろうか。「もう、なんなの。誰もも手伝おうとしないしさ」。叔母が怒り始めた。
それでも従妹たちはタコをひっくり返そうとしない。
私は従妹たちに聞いてみた。「たこ焼きひっくり返したいんじゃなかったの」。
「ひっくり返したい」。従妹は答えた。
ここには何か問題がある。私はそう確信した。
2つの問題点
大人が主導する
問題点は2つあるように思う。第1に子どもたちがたこ焼きを「ひっくり返したい」と言っていたのに自主的にひっくり返さなかったことである。言い方が悪いかもしれない、厳密にはひっくり返すタイミングが分からなかったのかもしれない。つまり、子どもたちは怠惰だったのではなく、ただ分からなかったのかもしれない。
今回の場面では、大人である叔母が先に具材を鉄板に流し込み、たこ焼きを焼き始める。どこかのタイミングで従妹たちに作業のバトンを渡す必要がある。そのタイミングが曖昧だった。
私が考えるに、ここには大人に問題がある。先に作業をはじめ、子どもに作業を引き継ぐ大人がはっきりと指示を伝える必要がある。
叔母はただ一言「やってよ」と言っただけだった。それもぼそっと呟くように。
指示は言っただけでは意味がない。人が動かなければ、それは言ったことにならない。
では、どうすればよかったのか。子どもたちの目を見て、そして例えば「○○ちゃん、ここでひっくり返して」と言えばよかったのだ。とにかく相手の反応を見て、的確に指示を出していく。
指示を出すのは実は大人でも難しい。
多くの人が体験したことがあるであろうが、AED(自動体外式除細動器)の訓練では、事故が起きた際は「○○さん、救急車をおねがいします」、「△△さん、AEDをおねがいします」と必ず名指しで指示を出すように教わる。
これは人がやるべきことが分かっているにもかかわらず、自分から関わろうとしない、という心理をあらわしている。人は集団では求められなければ動かないものなのだ。
自分で状況を判断して動く。これは必要なことである。しかしながら他者にこれを過度に求めてはならない。
他者は何を考えているか。相手は(大方、これは上司に対してであることが多いのだが)自らの行動が集団において、相手において、悪影響を与えるのではないか、と危惧している。
ましてや、規則や作法が異なる集団にはじめて入ったときはなおさらである。有能な社員が転職した際に、転職先ではうまくいかないケースがあることが、これを証明している。
大人が主導しなければならない。子供は大人の指示を待つものである。 自主的に行うべき、というのは大人本意の考えである。
ルールが確立されているか
第2の問題として、家庭での決まりごとが確立されているのか、ということがある。
実は、これが私自身も頭を悩ましているのであるが、子どもたちはスマホで動画を見ている。
使っているスマホは叔母のものだ。私の考えではスマホのルールに関しては叔母が決めるべき、と考えている。仮にスマホがタコ焼き機に接触して故障しても私の問題ではないからだ。
原則がはっきりしていなければならない。食事中にスマホはOKなのか。それとも子供が周りの状況をみて自主的に行動することが求められるのか。これは各家庭が決めることである。
基準が曖昧なまま(自分の中でのみ基準がある)では駄目である。規則は組織で共有されて、運用されてはじめて意味を持つ。リーダーはルールが確実に運用されているか確認しなければならない。
教師の責任
教育において教師には明確な指示が求められる。
誰が答えてもいい、という問いかけに生徒が一人も手を挙げないのはしょうがない。その質問の答えは生徒の自主性に任せられているからだ。
突然キレる教師がいる。これは災害的だ。キレるまでに黄色信号を点灯させなければならない。
生徒がしてはいけないこと、するべきこと、達成されるべきレベル、期限を明確にしなければならない。これを怠ったのは教師の責任である。
規則の重要性
つまり、組織やグループにおいて作法や規則がどれほど重要であるか。これを今回のタコパ―のケースが示してくれている。
物事を滞りなく進めたいのであれば、組織には規則が必要である。責任者(リーダー)は誰か、実働部隊は誰か、何を行うか、いつ行うか、いつまでに行うか、これをはっきりさせなければならない。
なぜなら人間とは共感の生き物であり、時として怠惰な生き物だからである。物事に積極的に関わることが難しい人がいる。組織で動くと個人が関わることが難しいケースがある。
これは私が過去に受けた採用試験の事であるが、「自らが組織にどのように貢献できるか」という質問を英語で受けた。
英語で返さなければならないのであるが、集団の誰も答えようとしなかった。明らかに他の相手の出方をうかがっていた。結局、私が先陣を切るまで誰も手が上がらなかった。
今回のタコパ―の件に関しては、私が大人としてもっと関与するべきである、という意見もあるだろう。しかしながら、私はこの手の件には口を出さないことにしている。
というのも、私の叔母は自分の型をもっていて、それを譲らない人間だからだ。過去に私がたこ焼きや焼き肉を焼くことを叔母と共に行ったことがあるが、私の肉の焼き方や具材の居れる順番、たこ焼きをひっくり返すタイミングについて、「ああだ」、「こうだ」、文句を言われたことがある。しまいには「まったく役に立たない」だ。
叔母は40歳を過ぎている。もういい大人である。正直に言って叔母とはそりが合わない。
これまで、ことあるごとに私は自らの意見を叔母に率直に伝えてきた。返ってきたのは文句と喧嘩。時には数週間口をきかないこともある。
私は考えを改めた。叔母には変化を期待しないことにした。何も指摘せず、怒らないことにした。指摘とは、怒りとは、相手が”変化する”ことへの期待の裏返しである。私はもう叔母には変化を期待しない。
しかし、小学生、まだ子供である従妹たちは別である。彼女たちには誤った教えを与えたままで終わらせたくなかった。
明らかに彼女たちはなぜ叔母がキレたのか理解していなかった。
私は彼女たちが本質的には悪くないこと。自分たちが自主的に動いた方が良いこと、を伝えた。
たこ焼きといえどもチームで役割分担している以上、一つの組織である。リーダーが必要か、考えなくてはならない。必要ならば、リーダーが必要な意思決定を行わなければならない。
ちなみに私と叔母は決して仲が悪いわけではない。ただ、あらゆる分野で考えが合わないだけである。
これはいかなる組織においてもいえることであるが、良い組織と仲の良い組織は違う。
仲が良い組織に越したことはない。しかし、そうはならないのが普通だ。組織とは思想のことなる人々の集まりである。一見メンバーが仲良くしているようでも、見方を変えれば、誰かが周りに合わせているに過ぎないことが多々ある。
組織において重要なのは結果であり、メンバー個人の貢献である。たとえ組織にイジワルがいても、癇癪持ちがいても、偏見思想がいても、第一には各人が組織に貢献し、組織として結果を出すことである。リーダーは結果をだせるように組織員を動かさなければならない。
家庭においても思想や性格の不一致は禍をもたらすことがある。
しかしながら、どこかで妥協点を見つけ、お互いに暮らしやすい環境を見つけることも家庭運営において肝要である、と考える。
今日も皆さんが幸せでありますように