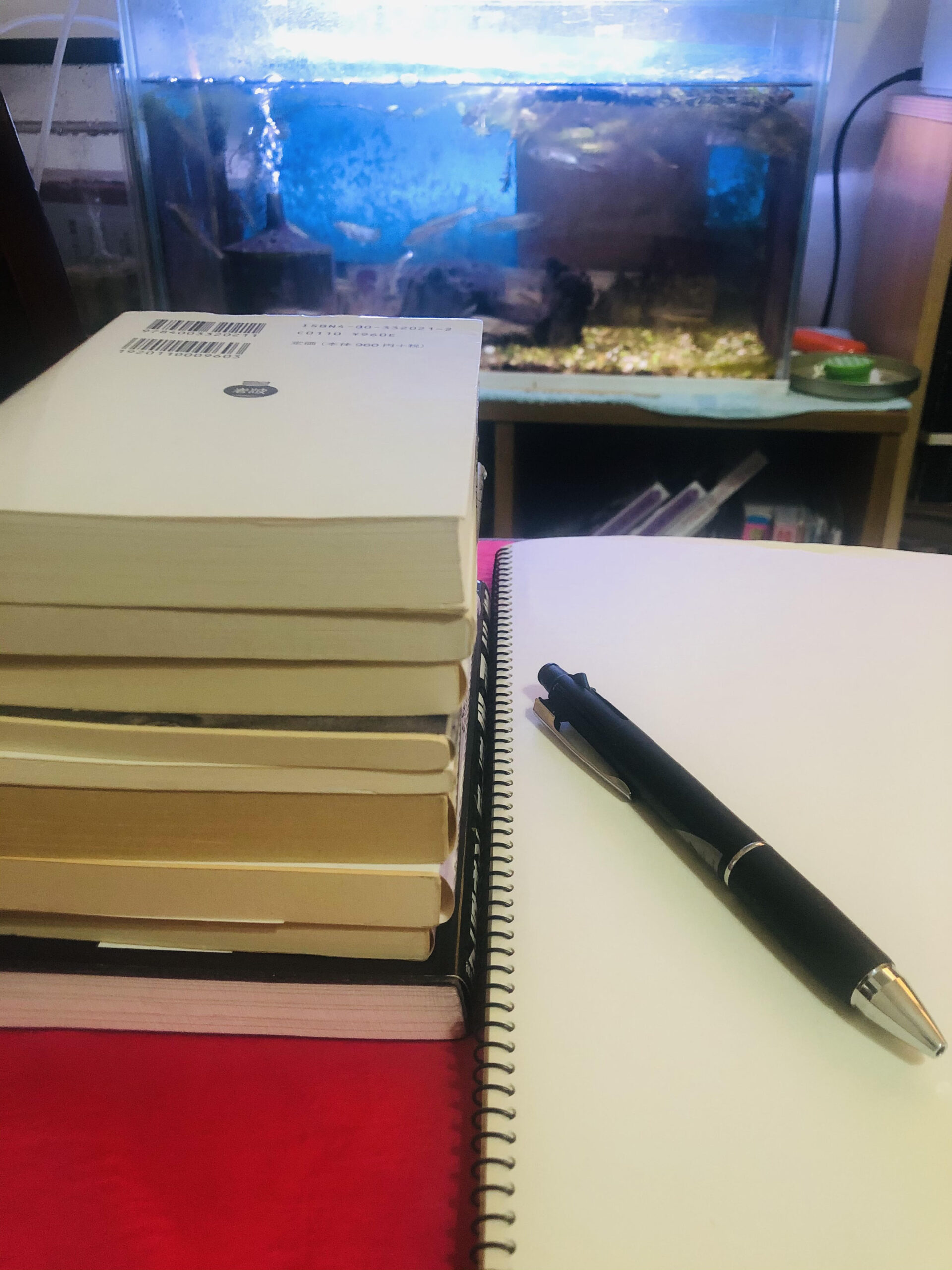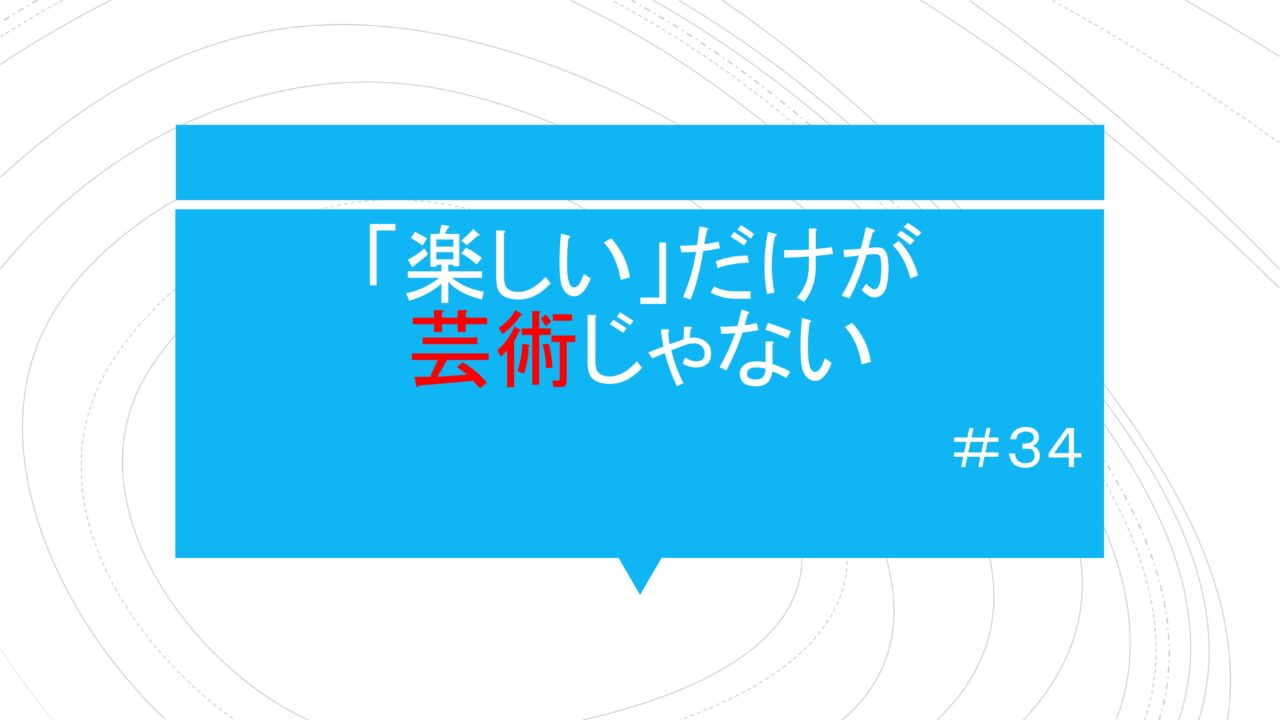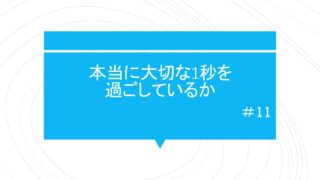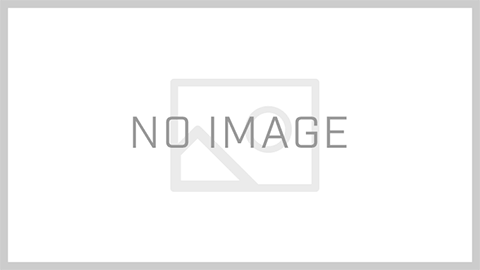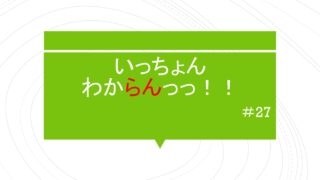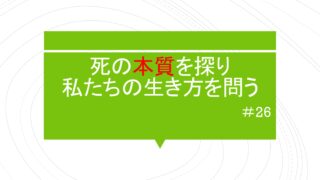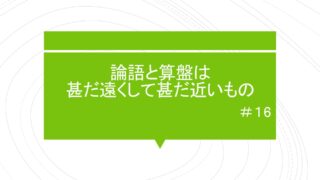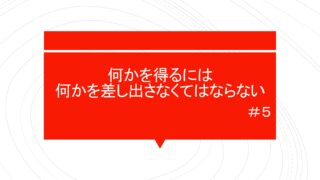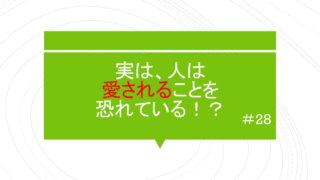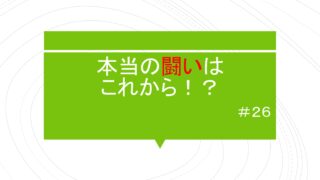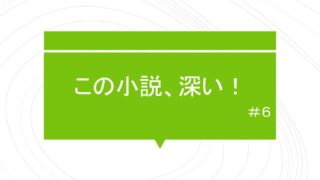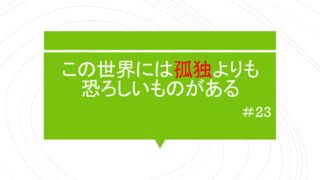うらみわびの【きょう考えたこと】第34回
コロナ禍における芸術の必要性
はたして芸術は必要なのか。これが問われたのが今回のコロナウイルスによる社会の停滞である。感染防止のために不要不急の外出の抑制が求められてきた。そしてライブハウス等での人の集まる場所での集団感染(クラスター)が発生すると、ライブや公演などの芸術面の活動が不要不急の活動として止められた。
この判断の根底には「芸術は社会になくても生きていける」という考えがある。コロナはいつまでも続くわけではないので、実際には「(今、)芸術は社会になくても生きていける」か、ということを問わなくてはならない。私は「今も芸術は必要だ」と考えている。
社会を考える際、私たちは主に経済面で考える。生活を送るお金があればなんとかなる、というわけだ。コロナ禍のなかでは雇用や休業補償の課題がこれにあたる。
一方で私たちが忘れがちなのが精神面でのことである。人間は心が健全であってはじめて日常の生活を送ることができる。元気でいる時には考えが及ばないのであるが、元気でいられるのは心が健康だからである。
現在のコロナ禍で、私たちは未知の世界に対処していこうとしている。とてつもないストレスだ。私たちの心は疲弊している。実はこんな時だからこそ芸術は必要なのである。私たちの心を満たすために。
教養としての芸術
コロナ抜きにしても芸術は本質的に軽んじられるべきではない。孔子は芸術は教養と捉えており、特に音楽を重んじた。
詞に興こり、礼に立ち、楽に成る。
((人間の教養は)詩によってふるいたち、礼によって安定し、音楽によって完成する。)
※訳は金谷治 訳(『論語』岩波文庫(1999))による
ここでは音楽が教養の最終形態として位置づけられている。音楽とはそれぞれがもつ経験と知識から論を抽出し、それを周りの人と和すことによってひとつの調べを奏でる、ということだ。音楽こそが社会なのである。
 |
|
価格:1,177円 |
![]()
苦難を見せるのも芸術
苦しい時こそ芸術を
コロナの状況においては音楽は既存のもの(CDや映像資料など)によって愉しめばよい、という意見がある。そこに一定の妥当性を感じつつも私はある危機感を抱いている。それは芸術の生産が止まること。それにより現在において芸術の空白が生まれる。これはあってはならないことだと考える明るい芸術もあれば苦難の末に生まれる芸術もある。現在のような苦しい時だからこそつくる価値のある芸術があるのではないか。例えばロシアのドストエフスキーは政治転覆の疑いを掛けられて結果、シベリアへ流されたが、ここでの4年かの服役生活を『死の家の記録』として残している。この小説(と呼んでいいのかな)は読み物としては乱雑で整理されていない。しかし、そこに書かれているのはドストエフスキーが見たリアルである。厳しく残酷な刑罰、凶悪化する囚人たち、それでも生きる希望を見失わなかった自分など……。娑婆にいる自分では想像もできないことがそこにはある。
苦難だけじゃない。音楽アルバムをジャケット買いやタイトル買いしたときに、思わず名曲に出遭うことがある。あれと似たようなことが小説でも起こることがある。『死の家の記録』では、実は刑務所内の方がお金のもつパワーが娑婆よりも大きい、という著者の気付きが書かれている。これは意外ではないか。刑務に服するだけだと思われている刑務所内で、囚人たちは自らの生活を成り立たせるために職を持つようになる。そしてお金を囚人たちの中で回しながら生活をしている。散髪を請け負う囚人がいれば、散髪に使うハサミやカミソリを研ぐ囚人がいて、高利貸しまで存在する。そう、刑務所内にも経済が存在するのである。これは驚きだった。
 |
|
死の家の記録 (新潮文庫 新潮文庫) [ ドストエフスキー ] 価格:935円 |
![]()
小説や新聞、雑誌など書物だけとっても私たちに新たな世界を見せてくれる。そこが芸術の大きな力である。苦難の芸術は苦難の世界を見せてくれる。きれいな世界だけでは人はよくならない、と考える。真の優しさとは何か。愛とは何か。厳しさとは何か。それは苦難の上にこそ成り立つのではないだろうか。だからこそ、私たちには喜びの世界と苦難の世界、両方が必要であり、両方を見せてくれる芸術が必要なのである。
これからの心の健康のために
そしてなにより芸術家の経済面での支援が必要である。芸術家の没落は将来的には文化面においての大きな損失である。研究者の処遇改善が叫ばれる今日この頃であるが、芸術家のそれも同じ目的においてそうである。現在、芸術家のなかにはネットを駆使して新たな芸術の市場を構築している人もいる。私は生きるための心の健康。そして心の栄養となる芸術の重要性を再考させられる。